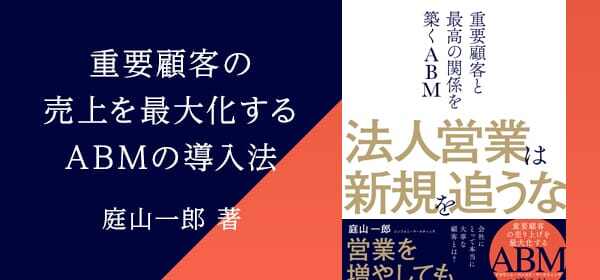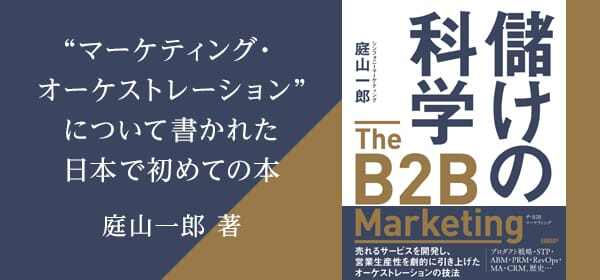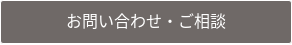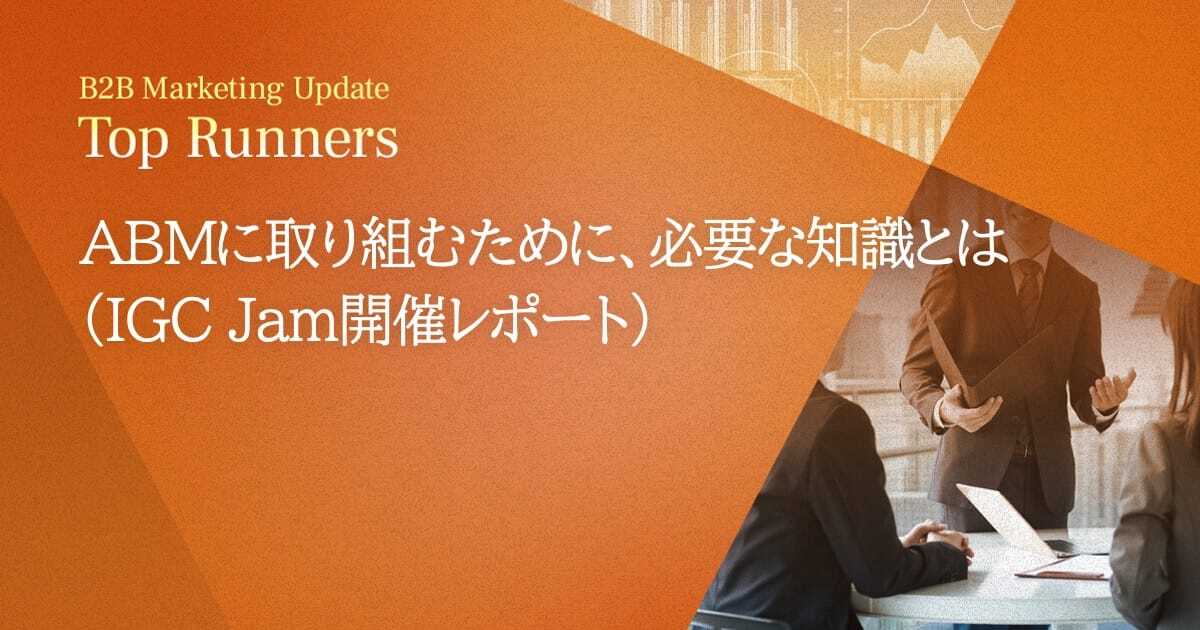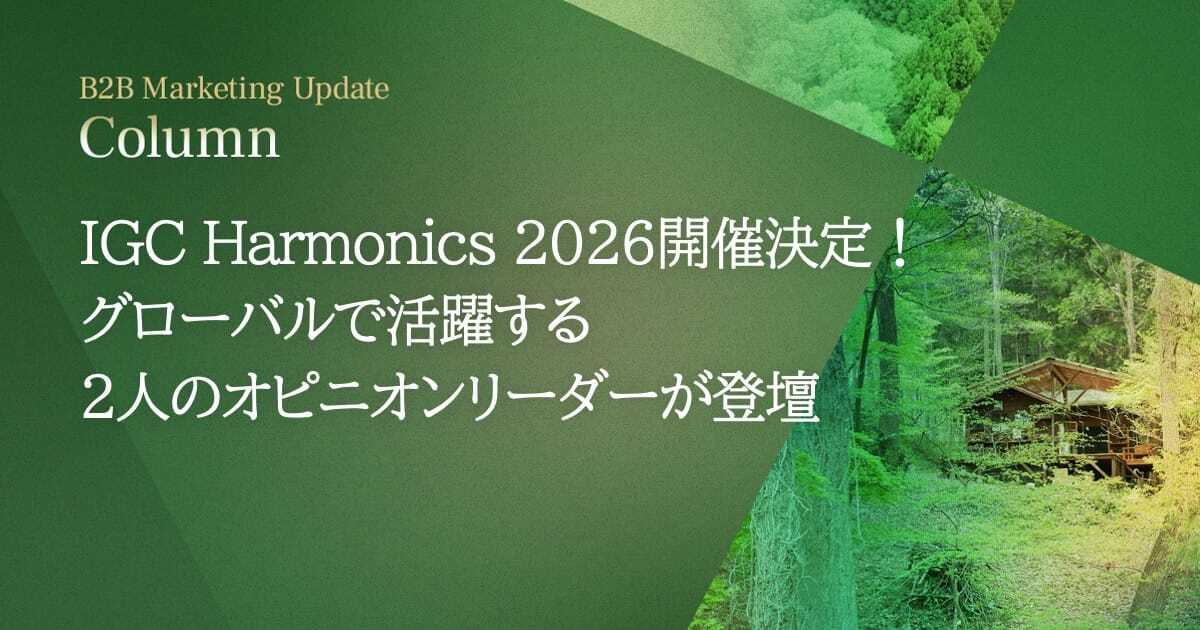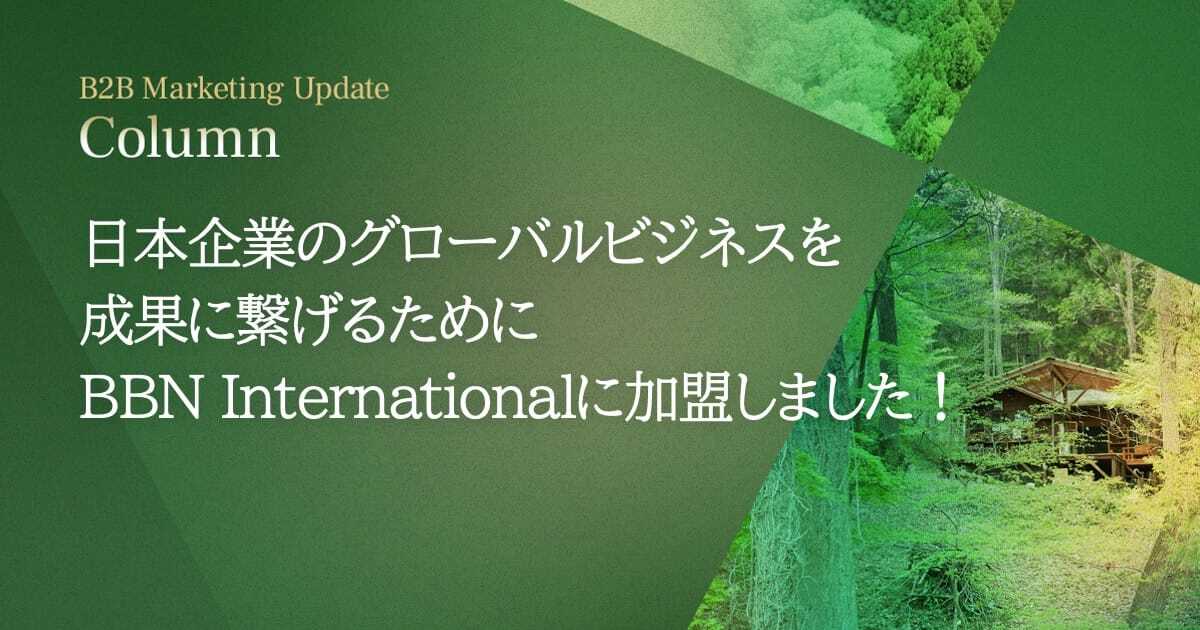ABM(Account Based Marketing)とは
世界のエンタープライズB2Bの世界では完全に主流となったABMの話をしましょう。
日本でも「アカウント・ベースド・マーケティング(ABM : Account Based Marketing)」という言葉を見る機会が増えましたが、マーケティングの先進国アメリカでも2013年頃から注目された新しい概念です。
シンフォニーマーケティングでは、以下のようにABMを定義しています。
全社の顧客情報を統合し、マーケティングと営業の連携によって、
定義されたターゲットアカウントからの売上最大化を目指す戦略的マーケティング
本当に価値ある大切な顧客に徹底的にフォーカスすることで、ターゲット顧客からの売上を最大化し、競合を排除する戦略的なマーケティングです。そのためには営業部門と話し合いを重ねながらアプローチしたいターゲット企業を定義し、マーケティング&セールスを設計しなければなりません。
ABM(Account Based Marketing)は
- One to One(1社のターゲットアカウントから始める)
- One to Few(2〜30社のターゲットアカウントから始める)
- One to Many(31社以上のターゲットアカウントから始める)
によってそれぞれ異なる設計を必要とします。
企業内のCクラス(役員クラス)をターゲットとする欧米ではOne to OneかOne to Fewから取り組むことが多く、今の日本でもOne to Fewでの設計が多いように見えます。
日本で成功するABMはOne to Many
しかし、シンフォニーマーケティングでは、日本国内のABMにおいて成功するのはOne to Manyだと提唱しています。それは、日本企業が欧米企業のセクター制(ターゲット市場ごとの組織)ではなく、技術や製品カテゴリーごとに縦型の組織を作っていることで、「自社」ではなく「自分の事業部」の顧客しか見えていないケースが多いからです。
こうした企業がABMに取り組み、他事業部の商材の中で高いシェアを持っているものと、顧客にとって良いシナジーを生み出す商材を開発し、それをマーケティング&セールスすることで、既存顧客の売上を最大化することが出来るのです。
製造業で加工機器と搬送システム、RFIDとBOM(部品管理システム)、IT業でプロジェクト管理システムとタレントマネジメントシステムなど、ひとつの企業の中で異なる事業部や事業所で作られて、顧客に販売されている製品やサービスで比較的容易にシナジーを効かせることが可能なことは多いものです。
そうしたもので、新たな価値【DoV】(Definition of Value)を生み出し、これのICP(Ideal Customer Profile:理想的な顧客プロファイル)に対してABMを展開するのが日本企業に最も合ったABMではないかと私は考えています。
次回はABMのターゲット選定(ICP)についてお話ししましょう。