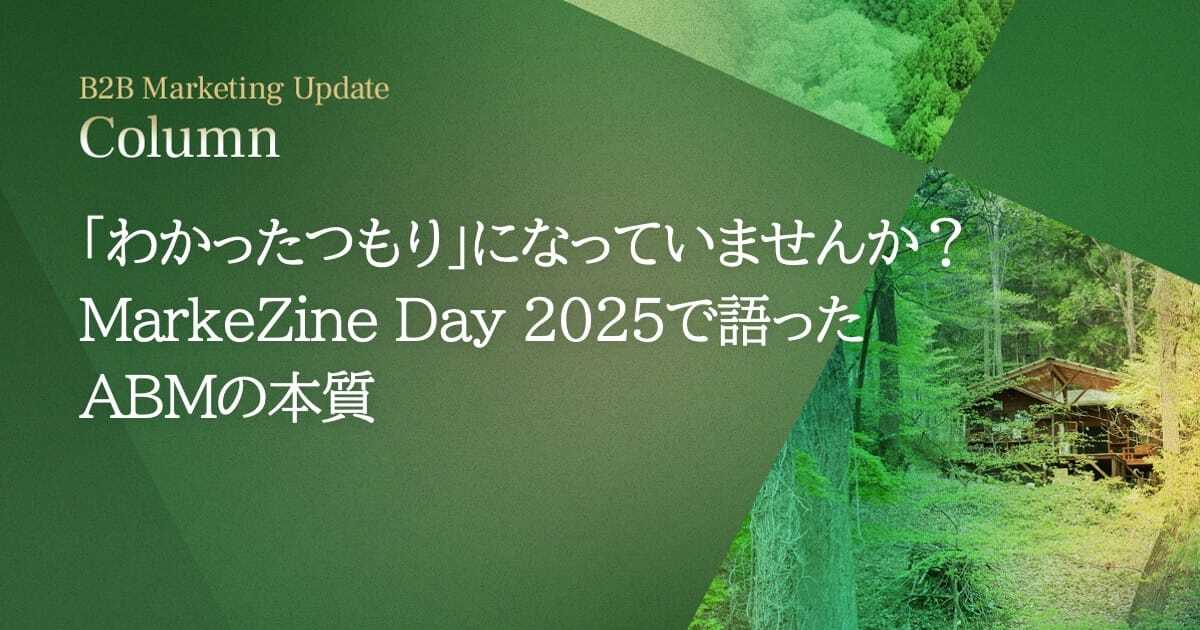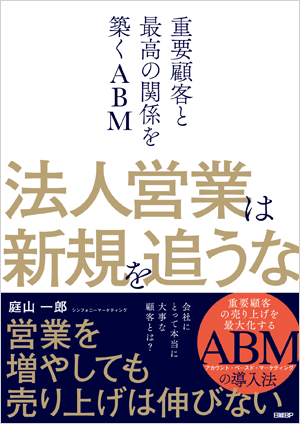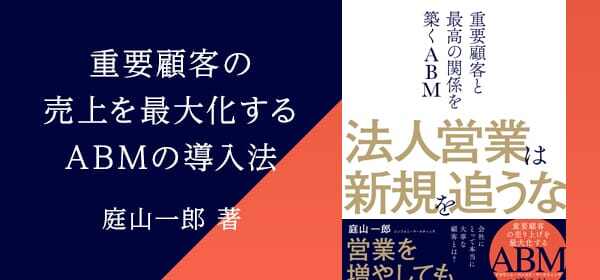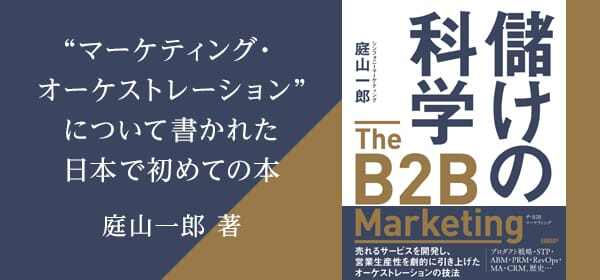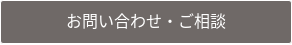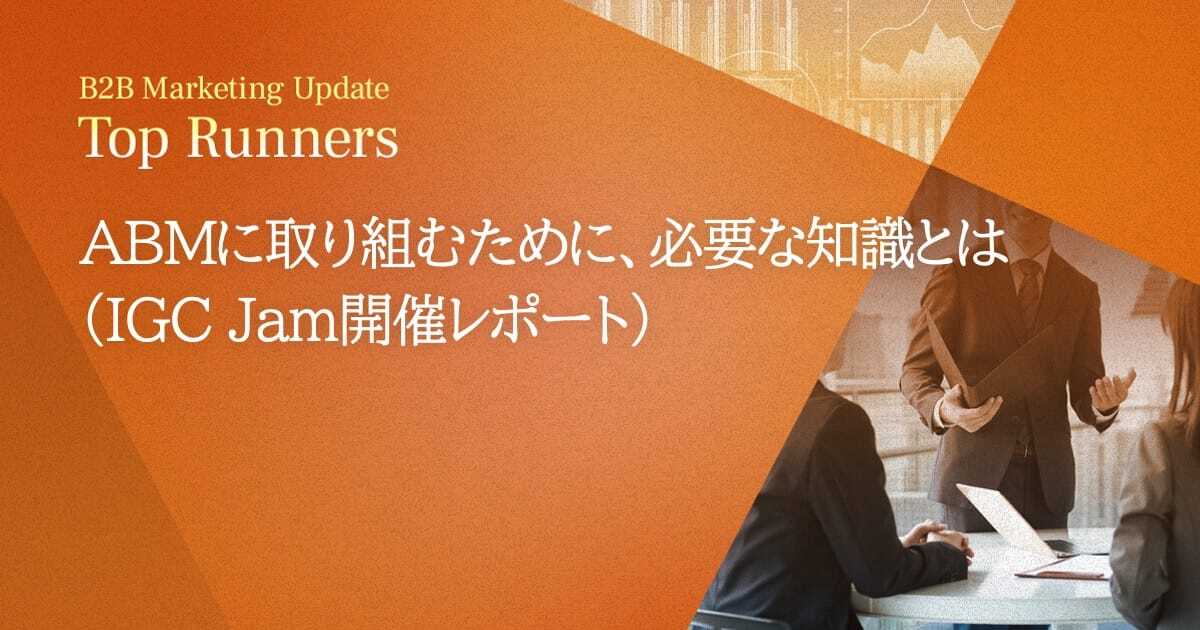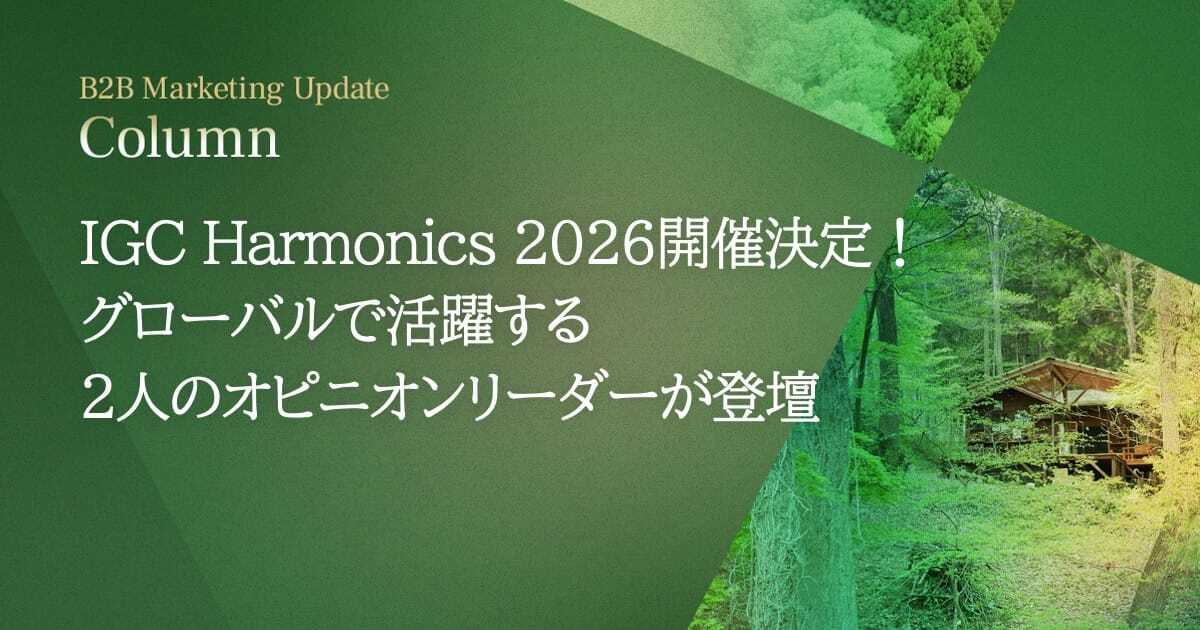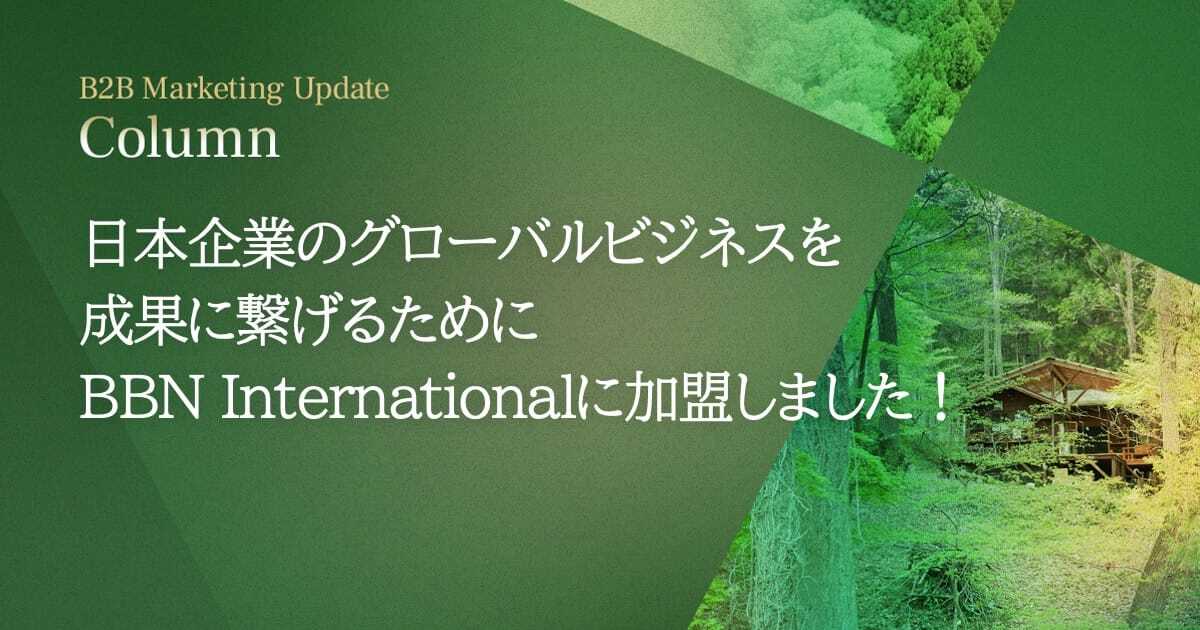2025年9月11日、MarkeZine Day 2025 Autumnにて、当社代表の庭山が株式会社WACUL代表取締役の垣内勇威氏と共に登壇いたしました。セッションテーマは「『わかったつもり』になっていませんか?庭山氏×垣内氏で紐解く“ABM"の本質」。垣内氏からインタビューを受ける形式で、庭山がABM(アカウントベースドマーケティング)について詳しくお話しをさせていただきました。
当日は多くの方にご参加いただき、ABMへの関心の高さを改めて実感しました。セッション後も「もっと詳しく知りたい」というお声を多数いただいたため、今回特別にその内容を登壇レポートとしてお届けします。
成功への鍵:ABMの重要な要素
①適切なターゲット選定:「伸びしろ」で選ぶ
ABMで最も重要なのは、適切なターゲット企業の選定です。多くの企業が「売上トップ10」や「業界トップ10」を選びがちですが、これが大きな落とし穴なのです。庭山がセッションで強調したのは、売上規模ではなく「伸びしろ」で選ぶことの重要性です。
「ある製品をたくさん買ってくれている。取引が伸びて、売上のトップ10に入っているけど、実はこの製品しか買ってくれていない」というケースこそ、クロスセルの大きなチャンスが眠っています。逆に「本当にこの会社ってもう伸びしろがない」というところにABMを展開しても、「嫌がられるだけ」になってしまいます。
②デジタル戦略の活用:バイイングシグナルを見逃さない
従来の「ゴルフに行ったり、お酒を飲んだり」という営業スタイルでは、顧客の課題形成段階にアプローチすることが難しいのです。しかし、デジタルツールを活用することで、顧客の潜在ニーズを可視化できます。
人と違い、デジタルは時間と肉体の制約がありません。ですから「どの企業のどの役職のどの部署の人がこの本を買ったか、この資料をダウンロードしたか、このウェビナーに登録したか」といったデータから、「この部署の人間が20回くらい見ています」「少なく見積もっても10人以上が1回見ていると思いますよ」という具体的な情報を営業に提供できます。これこそが「デジタルの空中戦でキャッチできる」情報なのです。
③営業との連携:反対勢力が多いほど成功する
意外にも、「全社あげてABMをやりたいです」という会社は結構失敗しています。逆に「俺の客に触るな」「俺の客に勝手にメールなんか出すな」とアカウントセールスチームが猛烈に反対するケースが一番成功しています。
なぜなら、売上のトップ10を任されているようなアカウントセールスチームは営業スキルがとても高いためです。「話を聞いてよし、説明してよし、売ってよし、人間関係もあって、誠実で信頼関係も獲得できる」という人間がそこにいるのです。 そのことから、彼らに新たな案件を渡せば、あっという間にクロージングができるというわけです。
日本企業が抱える課題
営業主導文化の功罪
日本企業では伝統的に営業部門が強い影響力を持ち、マーケティングは「販促部門」程度の扱いを受けることが多いのが現実です。アメリカではCMOが経営陣の一角を占めるのに対し、日本ではまだまだマーケティングの地位が低く、CMOの数も少数です。
しかし、ABMを成功させるには、営業とマーケティングが互いにリスペクトし合い、協力することが不可欠です。マーケティング担当者には「売上に貢献する」という意識を、営業担当者には「マーケティングの価値を認める」という姿勢が求められます。
経営層の関与の必要性
ABMは単なるマーケティング手法ではありません。どの顧客に、どんな価値を提供するかを決める「経営戦略」そのものです。ターゲット選定を営業に丸投げしてはいけません。経営層が主導して、全社的な取り組みとして推進する必要があります。
未来を共に創るために
ABMは「特定の重要顧客と最高の関係を築くことで、強い顧客基盤を構築し、収益を最大化することを目的とした全社的なマーケティング戦略」です。日本企業がABMを成功させるための第一歩は、営業とマーケティングの垣根を越えた協力体制の構築です。そして、デジタルツールなどを活用して顧客の潜在ニーズを可視化し、経営層のコミットメントのもとで全社一丸となって取り組むこと。
ABMは決して簡単ではありません。しかし、正しく実践すれば、日本企業の強みである「顧客との深い関係性」をさらに強化し、持続的な成長を実現できる強力な武器となるはずです。
2025年2月22日に発売した『法人営業は新規を追うな』では、本セッションでお話しした内容をさらに詳しく解説しています。日本企業がABMを成功させるために必要なナレッジと実践について、ご紹介していますので、ぜひご一読ください。