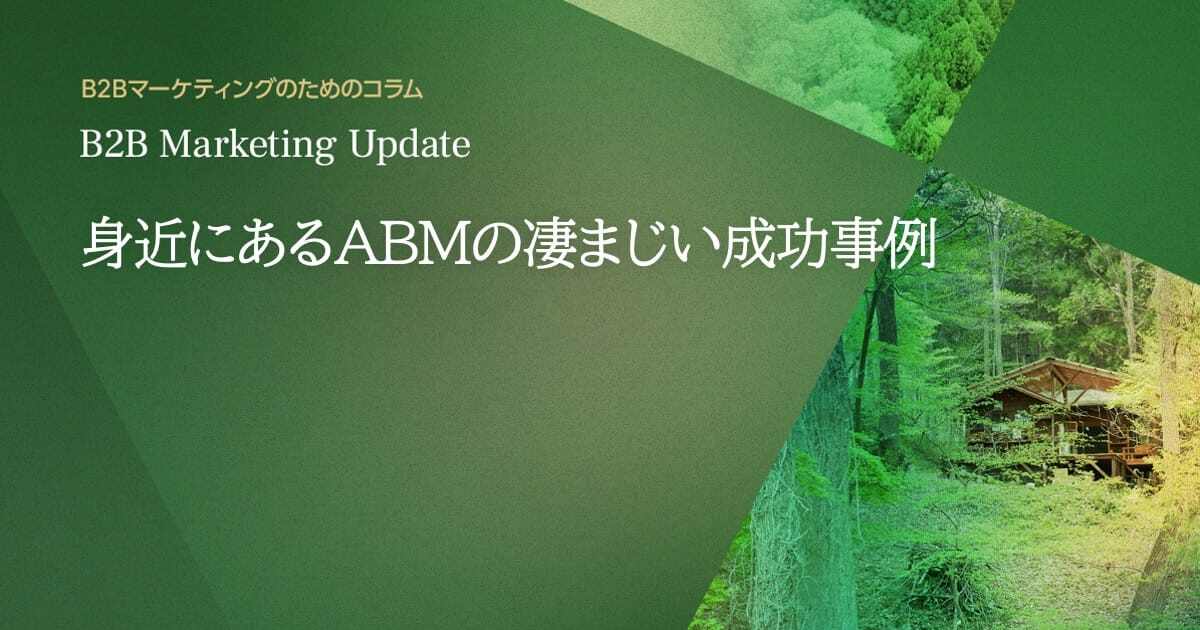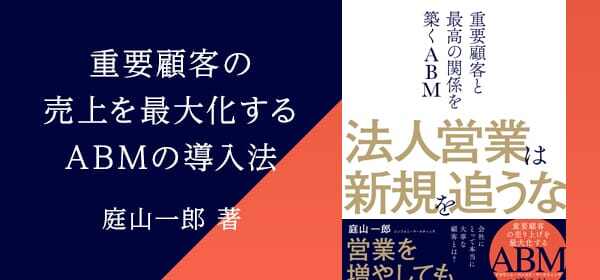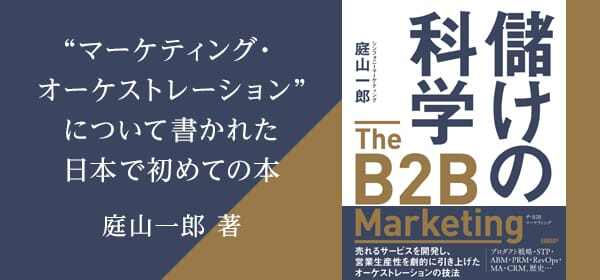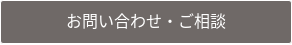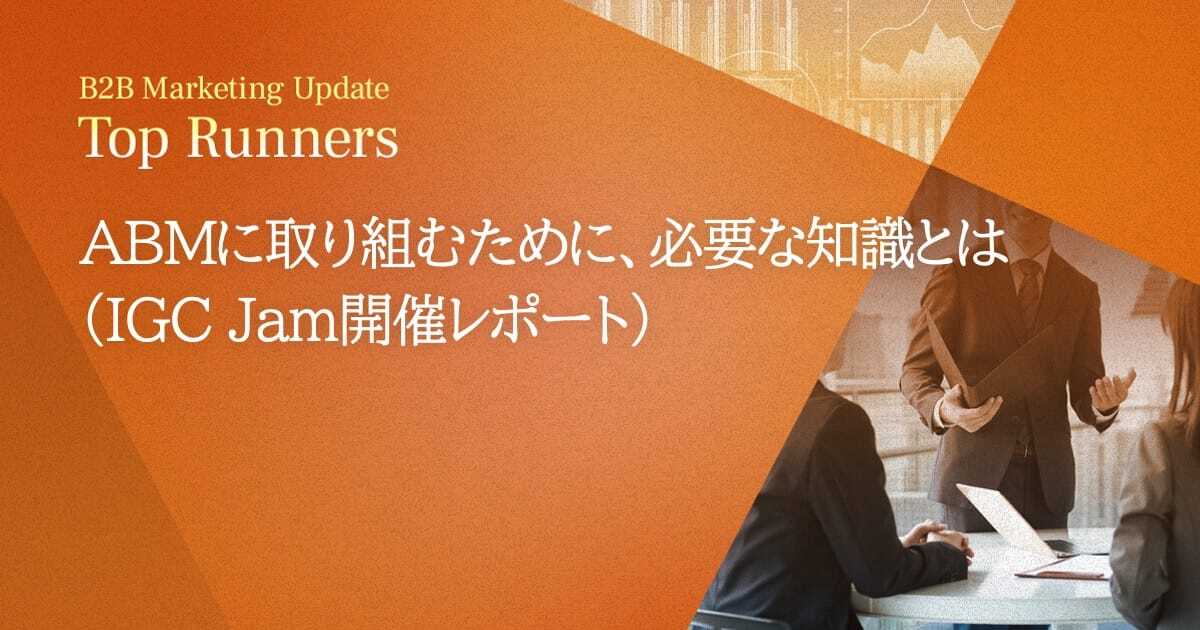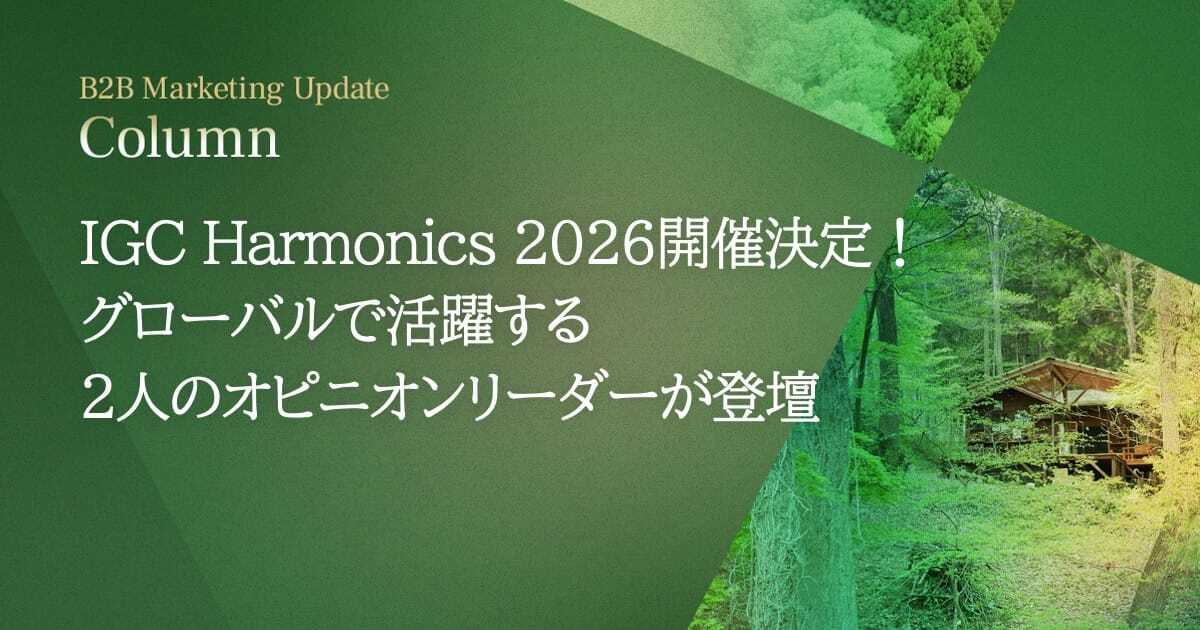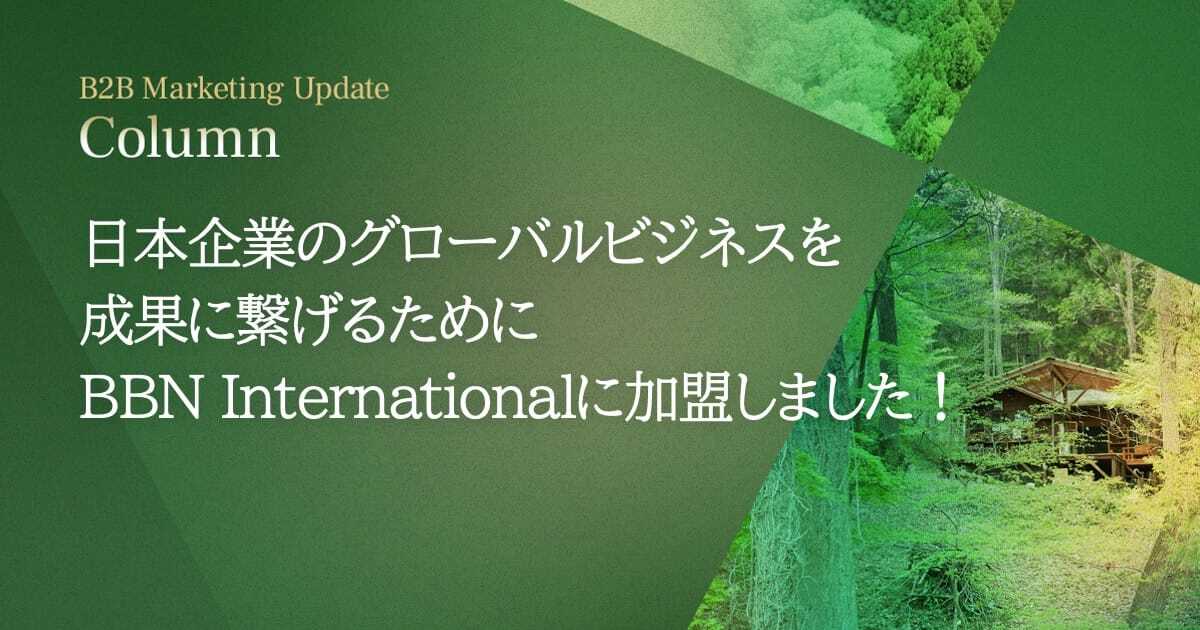3月にリリースした7冊目の本「儲けの科学 The B2B Marketing」の最後の章で、IBMが保有するエグゼクティブ向けの研修施設である【天城ホームステッド】を紹介しました。
2014年に米国アトランタ生まれのシルバーポップというMA(マーケティングオートメーション)をIBMが買収し、日本市場にもリリースしました。私の会社はIBMが買収する以前からこのMAの日本ユーザーをサポートしていた関係で、最初からIBMのパートナーとなり、この【天城ホームステッド】で研修講師を務めることになりました。
JR伊東駅でお土産の干物屋さんを冷やかしながら待っていると、この駅には不似合いなIBMロゴの書かれた大型バスが迎えに来てくれました。

そのバスで山道を30分以上走ると、「こんな山奥に?」と驚くような施設があります。高級リゾートか、ゴルフ場のクラブハウスのような建物で、中に入ると階段教室があり、大きなピクチャーウインドウの外にはゴルフのグリーンがあり、その向こうには富士山が観えました。宿泊は全室個室で、ホテルかと思うような食事が用意され、さらに夕食後は浴衣に着替えて懇親会を行います。

研修の翌朝、私は夜明けを待って周辺を散策しました。静かな天城の森の中にある石と木を組み合わせた広大な建物と、東京から数時間の距離が、集中できる環境を創り上げています。
IBMがこの施設を建設したのは、もう50年以上前の1968年です。1945年に第二次世界大戦が終わり、敗戦で焼け野原になった日本は朝鮮戦争の特需で経済復興が始まり、世界の奇跡と言われた高度経済成長が始まりました。この経済成長を牽引したのは各産業をリードする日本企業です。旧財閥の伝統企業はもちろん、当時は新興企業だったソニー、パナソニック、京セラなどの製造業、清水建設や鹿島建設などの建設業、三菱地所や三井不動産、森ビルなどのデベロッパー、ダイエーやイトーヨーカ堂などの流通業、通信、商社、金融などのサービス業が急成長していました。
IBMのターゲットは、それらの企業がこの先10年以上にわたって継続するであろう、メインフレームを中心にしたIT投資だったのです。各産業のトップ企業をターゲットに選定し、その情報システム部門と密接な関係を構築することは既に出来ていました。また社員を常駐させることで、オペレーショナルな課題も解決していました。しかしそれらの企業でお財布を握っているのは経営幹部です。彼らを説得しなければ稟議書は通りません。
その仕掛けとして創られたのが天城ホームステッドです。7万㎡の広大な敷地に建つ7000㎡の施設、道路からはIBMのサインとゲートしか見えず、その奥に何があるのかは判らない設計になっていました。
ロビーの壁にはここで研修を受けた日本経済の立役者の写真が並んでいました。
トップマネジメントですからITの専門家ではありません。恐らくIBMはここでコンピュータやメインフレームの話はしなかったでしょう。世界有数の経済学者やアナリストを講師に招いて語ったことは、世界経済の未来であり、企業戦略であり、人材育成であったはずです。これから爆発的に成長する日本企業に対して、当時のIBMがマントラのように唱えていたのは
「機械は作業をしなければならない、人間は考えなくてはならない
(Machines should Work, People should Think)」
という言葉でした。
IBMが説いたのはこれだったのだと思いました。作業は(高い能力を持つ)人にやらせてはいけない。(優秀な)人は考えることが仕事である。
企業がITに投資するのは目的ではなく手段です。目的は企業の成長であり、利益を上げることです。ならば、コンピュータのことはIT部門とIBMに任せて、経営者は未来を創りましょう、これがIBMのメッセージでした。
そして、この天城ホームステッドがオープンしてからの50年間で、IBMが日本市場から獲得した売上は30兆円を軽く超えます。
ABMのこれほど戦略的な成功事例が他にあるだろうかと思いました。もちろんこの時代には未だABMという言葉も概念もありません。しかし、これは間違いなくABMであり、世界でも最も成功したABM戦略のケースとして語られるべきことだと思います。
早朝の施設内を散策しながら、50年前にここにこれだけの投資をした戦略眼と、それを実行して見事に日本市場で大成功を収めた当時の人々に想いを馳せました。
こうした事例から学ぶコトは本当に多いのです。
日本のB2Bマーケティングは欧米の先進国から大きく遅れています。しかし、世界の大手企業の多くは日本で大きくビジネスを展開しています。それらを注意深く観察することで、世界水準のマーケティングを知る手がかりになるのです。