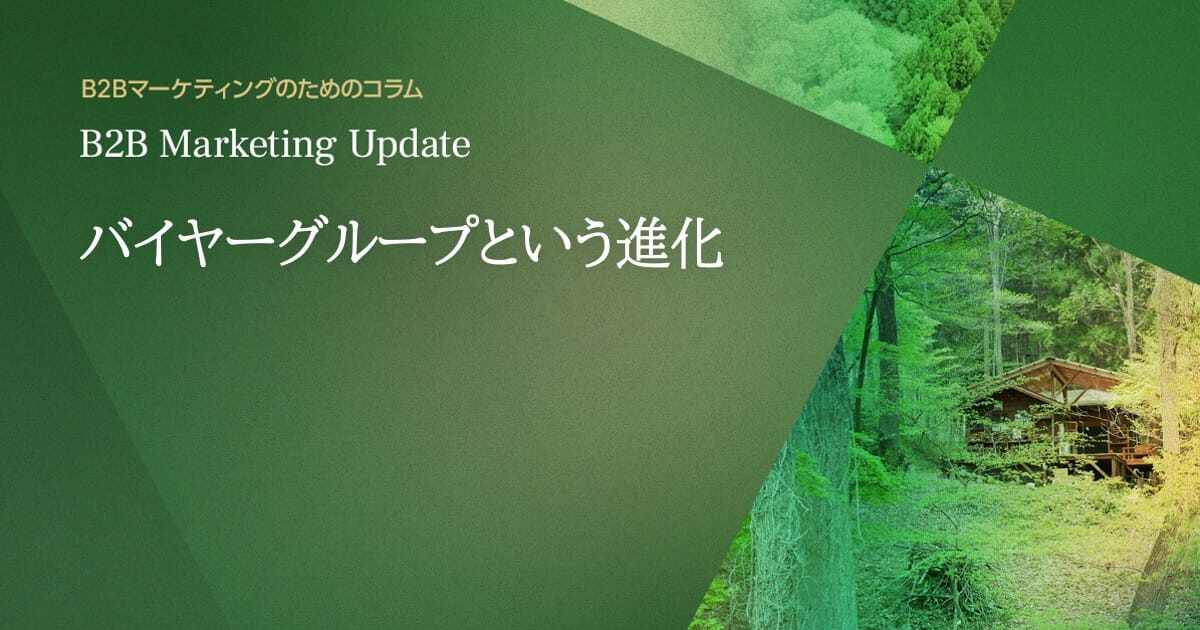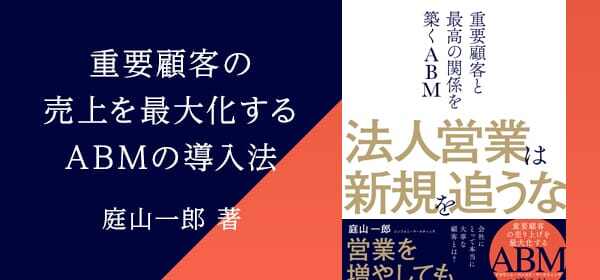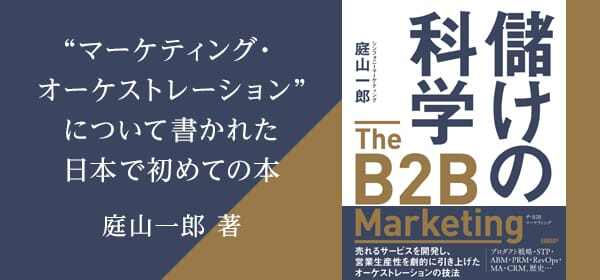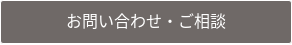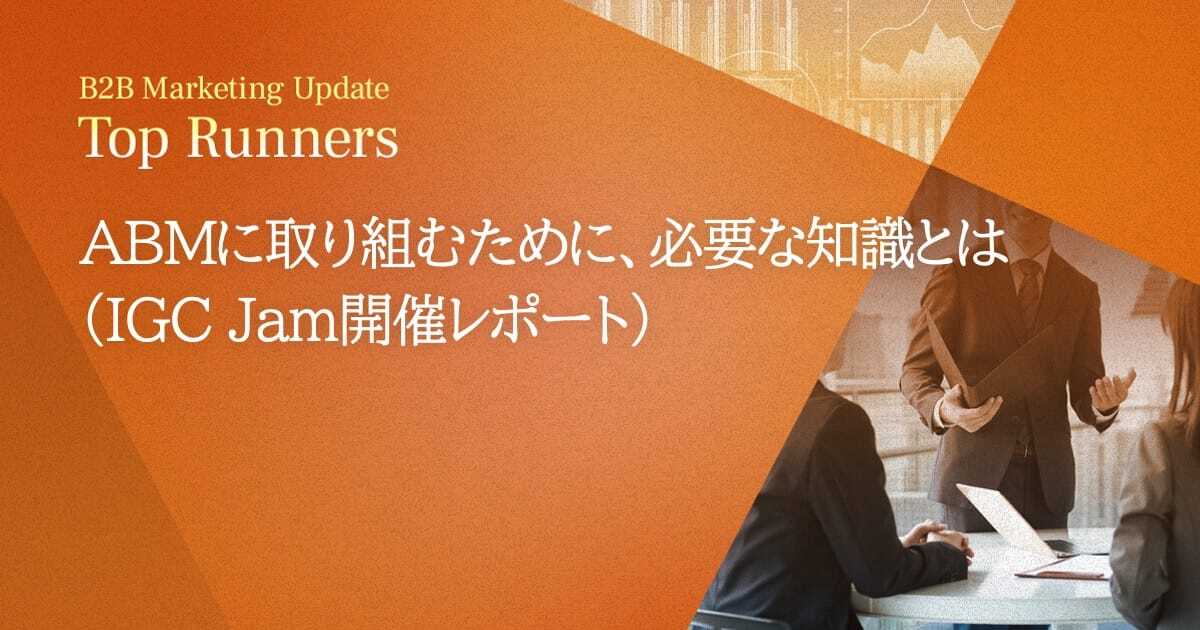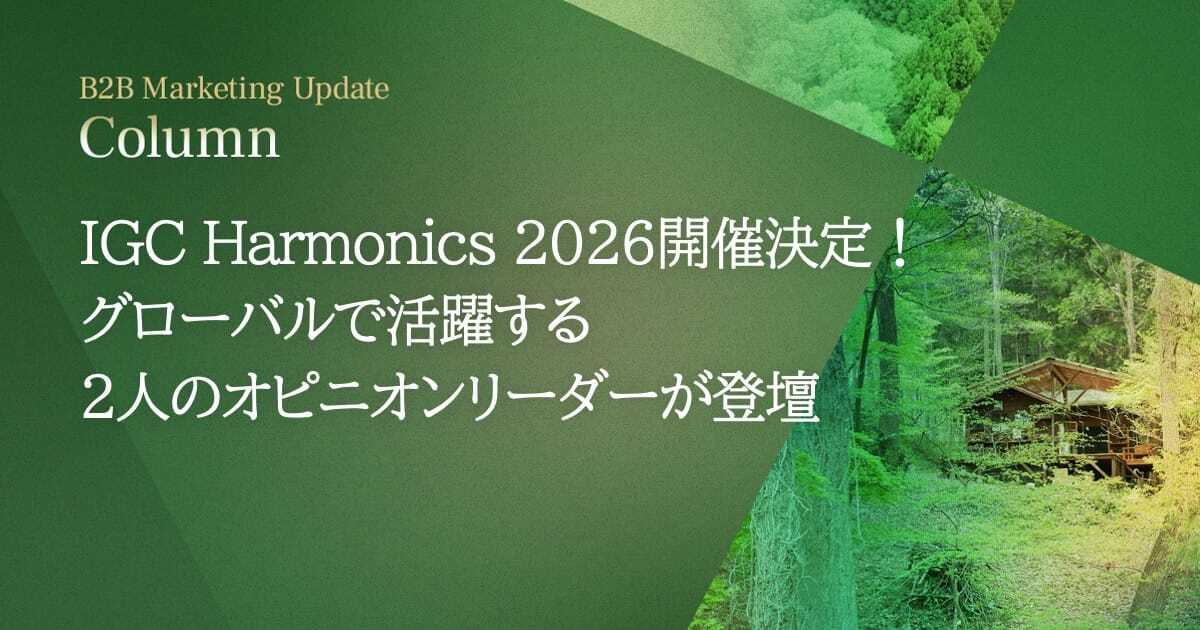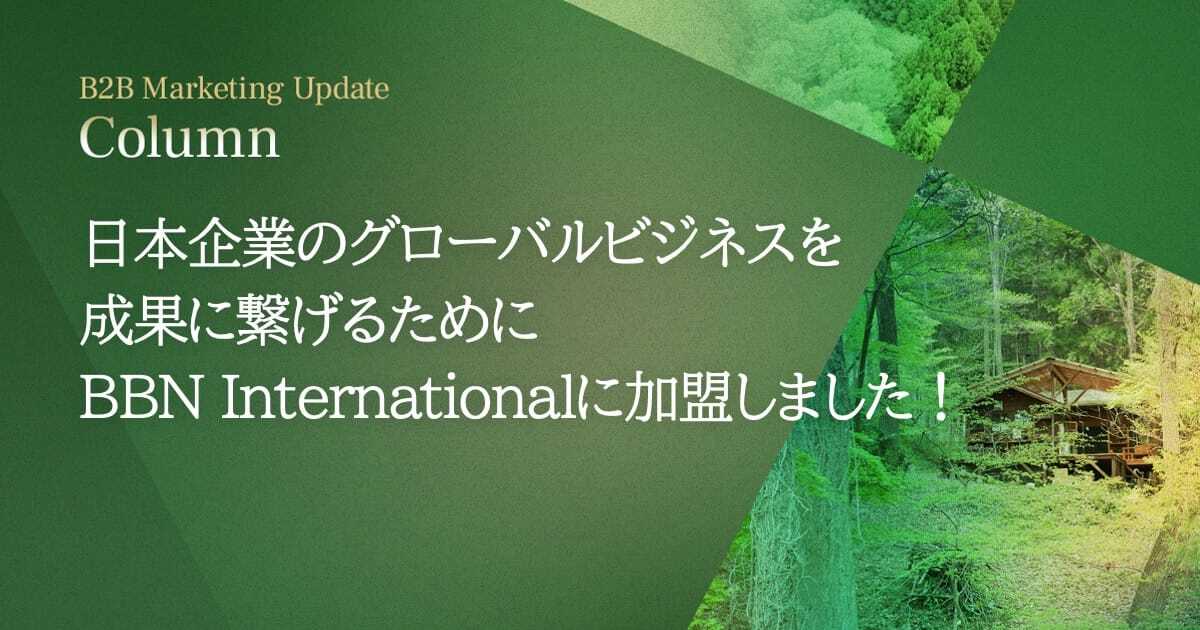今、欧米のB2Bマーケティング先進国で大きな話題になっているキーワードに「Goodbye MQL」があります。全文を引くと
「Goodbye MQL, It’s time to talk about Buyer group」というものです。訳すと「MQLよさようなら、さぁ、バイヤーグループについて語りましょう」です。
MQLとは「Marketing Qualified Lead」の略で「マーケティングによって作られた案件(商談)」を意味します。
現代のB2Bマーケティングのスタンダードモデルは、3年前にフォレスターリサーチによって買収されたシリウスディシジョンズが2006年に発表し、以来バージョンアップを重ねてきた「Demand Waterfall:デマンドウォーターフォールモデル」ですが、このモデルの中で重要なプロセスとしてMQLがありました。マーケティング活動によって創られ、アポイントまたは訪問承諾という形で営業部門に供給される案件のことです。それ以来、世界中のB2Bマーケターはいかにして良質なMQLを営業部門に供給するかを競っていました。
ところが、2023年頃から、シリウスディシジョンズを引き継いだフォレスターリサーチが、上記のように個人である「MQL」から購買を検討する集団としての「Buyer Group」にフォーカスを変更しようと提唱し始めました。そのアナウンスをした米国テキサス州のオースチンで開催されたカンファレンスには私も参加していましたが、聴衆の間からは
「なんでGoodbyeなんだ?」
「今までの努力は何だったんだ」
「変えなくてならない理由は何なの?」
という声が多くありました。
このデマンドウォーターフォールの主任アナリストであり、友人でもあるテリー・フレハティ氏の説明によれば、大企業の場合、情報を収集する人と、実際に発注する人は違うことが普通なので、情報収集している人を個人として追跡すると、同じ会社の違う人から来た発注をマーケティングとは関係のない売上としてカウントしなければならない。これはマーケティング部門が受注に貢献していないことになってしまい、結果として多くのマーケティング部門の人が解雇されてしまった。しかしこれらの発注の多くはマーケティング由来であり、それを補足するためにあるタイミングから個人を追跡する「MQL」から、そのMQLをインフルエンサーとした集団、つまり「Buyer Group」に拡大することにした、とのことでした。
「Buyer Group」は未だ新しい概念で定義が決まっていません。呼び方も「Buying Group」「Buying Committee」などさまざまです。
基本的には10〜18人ほどの集団で、購入(導入)の意思決定に関わる集団で、その中の役割を「最終意思決定者」「リサーチャー」「インフルエンサー」などとしていますが、購入する案件や事案によってグループ構成や構成員が変化しますので、組織というよりもっとファジーな集団を指す場合が多いのです。
そういう意味では、日本のビジネスカルチャーに昔から存在した「稟議書にはんこを押す人」に近い概念かも知れません。
B2BマーケティングはAIなどの技術革新の影響を受けて進化を加速させています。そうした進化と、変わらぬ原理原則の綾織りで自社のマーケティングをデザインしてみることが重要だと私は考えています。