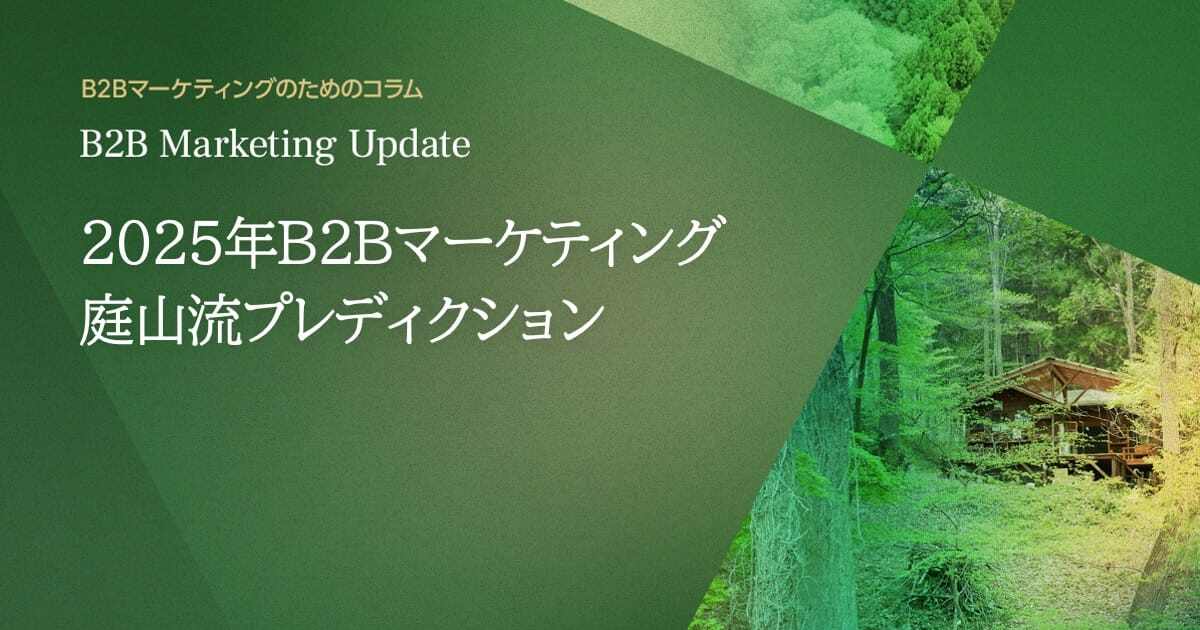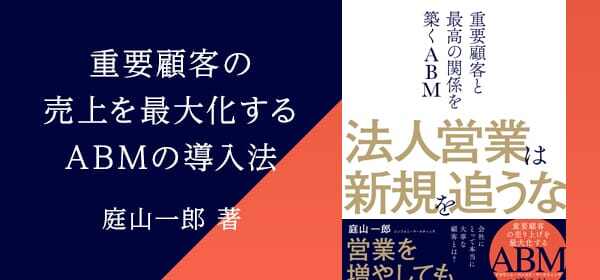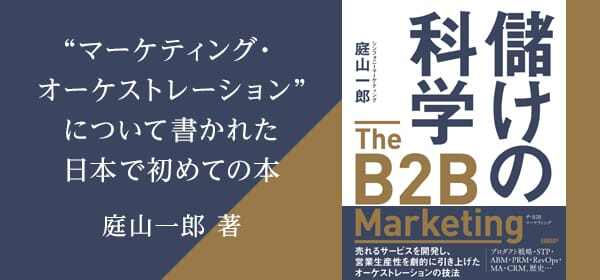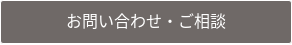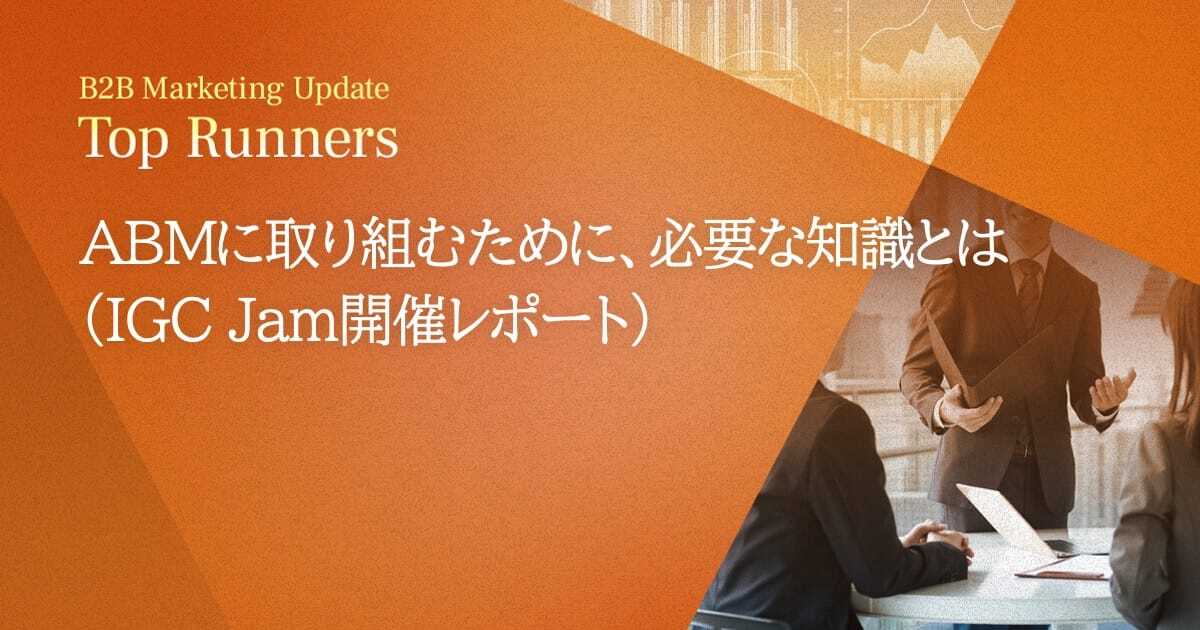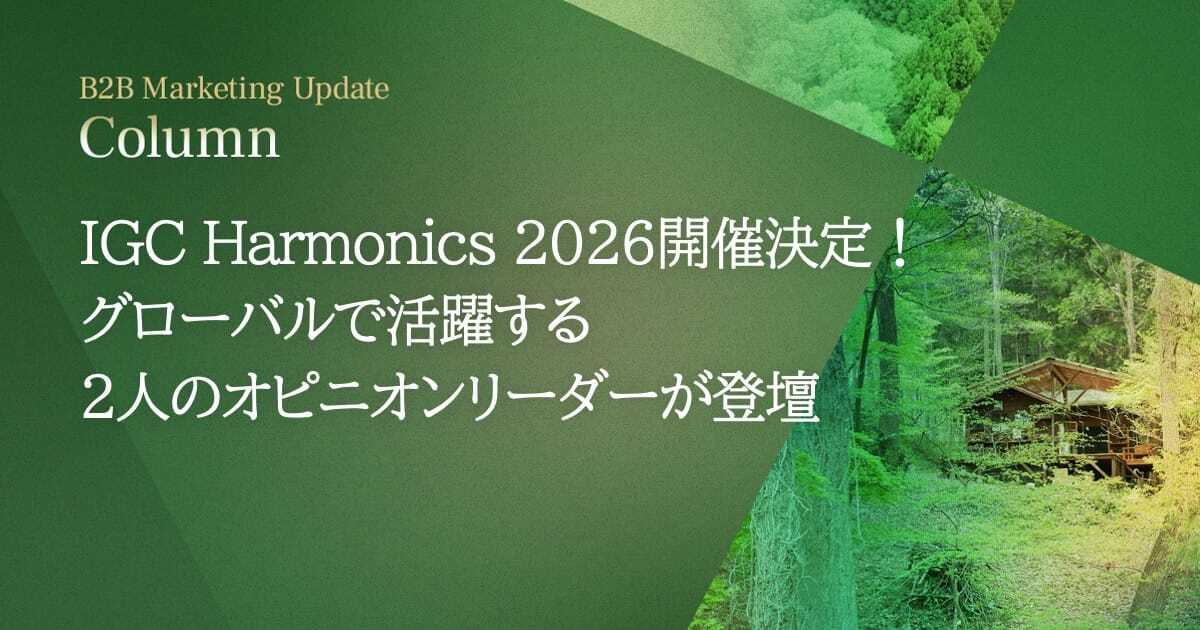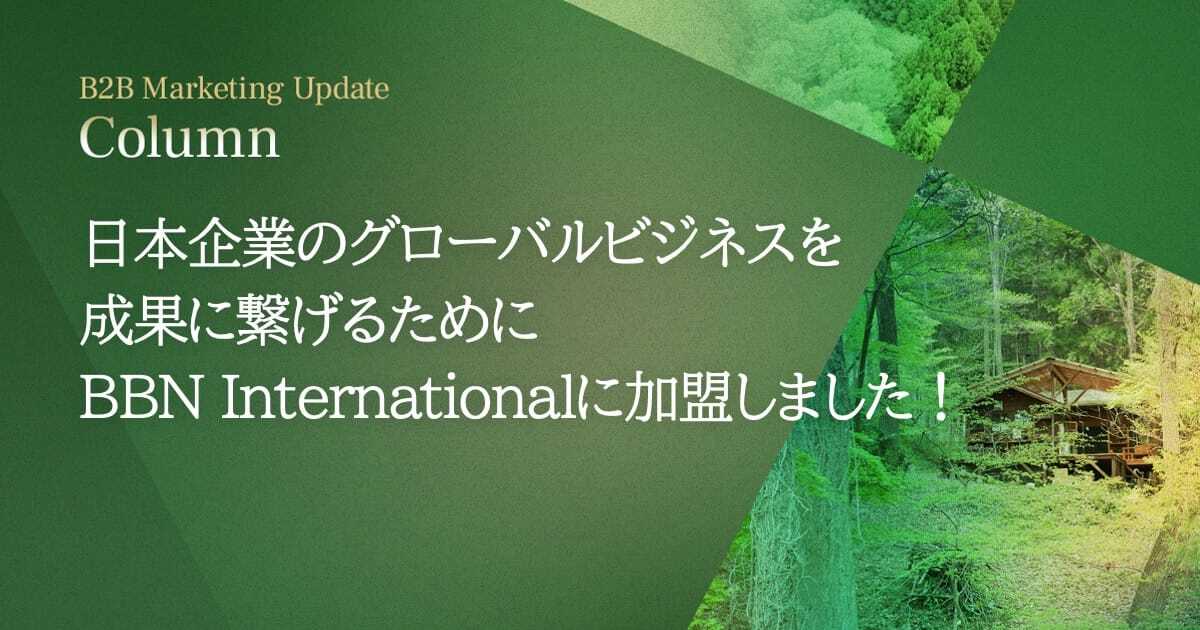明けましておめでとうございます。
本年もシンフォニーマーケティングをどうぞよろしくお願いいたします。
2025年、最初のコンテンツは今年、B2Bマーケティングがどうなっていくのか、私なりの予測を共有する内容で幕を開けたいと思います。
40年以上のB2Bマーケティングキャリアで、出会ったことがないくらいの激動期に
実はコロナ禍が収束してからの世界のB2Bマーケティングは、私の40年以上のマーケティングキャリアからしても経験したことがないレベルの激動期に入っています。
なぜ、激動期に入ったのか?その激動を受けて今年はどうなるのか?
我々はマーケティングのコンサルティング会社として、その激しい動きの源泉を見つけ、世界のトレンドをいち早くお客さまにお伝える使命があると思っています。
世界の今を、聞くだけ、読むだけでは意味がないので、現状を体感するために昨年も私と副社長の丸山とで手分けをして、世界中に出かけて、マーケティングのカンファレンスに参加してきました。
本日は、2人が世界中から「生」で仕入れたお話をしたいと思います。
2025年のB2Bマーケティングはこうなる?
1. 「GoodBye MQL」
過去20年間、世界のB2Bのマーケティングを牽引するアメリカのSirius Decisions(シリウスディシジョンズ)というアドバイザリーファーム(現在はフォレスターに買収され、フォレスターディシジョンズ)が、2022年に突然「GoodBye MQL」と言い始めました。正確に申し上げると「GoodBye MQL, It’s time to talk about Buyer Group」です。「もうMQL(個人)を追いかけることはやめよう。バイヤーグループについて語る時だ」という意味です。
なぜ今なのか?
その理由の1つが「顧客はカスタマージャーニーしていなかった」ということが判明したからです。具体的には、パイプラインの中身を細かく見たところ、B2Bの特徴であるリードタイムの長さから、途中でターゲットがいなくなる/ターゲットとは異なる人が入ってくるという状態を捕捉できず、MQLという個人をトレースした結果の受注率が1%しかなかったのです。
これでは大半のCMOやマーケティングマネージャーは解雇になります。
この事態を重く見たフォレスターディシジョンズは、大規模なリサーチプロジェクトを立ち上げ、再調査を実施。すると大企業の場合、個人のMQLが起点であっても、発注は別の部署の別の人から出ていることが多く、それを担当セールスが知らないことからマーケティング部門の貢献がなかった、となっていることが判明したのです。
この状況から、個人を追いかけるのはMQLまでにして、MQL以降はバイインググループ、つまり購買に関わる10人~15人のグループで見て、そこから発注が来たらそれはマーケティング由来、つまりマーケティングの貢献ということにしたのです。
私は、この考え方は日本でも取り入れるべきだと思っています。
2. シグナルベースドマーケティング
この「シグナルベースドマーケティング」という言葉を米国や欧州のB2Bマーケティングを牽引している英国で聞くようになったのは2021年以降です。
欧米では日本と違って名刺交換の習慣がないため、MA(マーケティングオートメーション)の中の個人情報の数がそもそも日本のように多くありません。つまり、ターゲット企業のバイヤーグループを15人と特定しても、その中の3人しかMAには存在しないということが珍しくないのです。こちらからコミュニケーション出来るのはその3人ということになりますが、その中の誰かが反応してMQLになっても他のバイヤーグループの人はアノニマス(匿名の存在)のままです。
しかし現代のテクノロジーを活用すれば、それが同じ企業の同じオフィスからのアクセスで、時間とブラウザからMAに情報を持っている3名以外と類推することができるのです。こうした信号を「バイイングシグナル」といい、これを補足してビジネスチャンスを見逃さないようにするのが「シグナルベースドマーケティング」です。
オンラインだけでなくオフラインの行動(資料請求やダウンロード)も重要なバイイングシグナルとして捉え、見逃さないことが重要です。
合法的に収集されたインテントデータ(意思を持ったデータ)の活用も重要です。
3. AIの時代
そしてこの2~3年、特にChat GPTが出てきて以降はもうAI一色です。実はアメリカのB2Bマーケティング業界はこの2年間で約10万人の人が職を失っています。マーケティング部門を大幅に縮小したり、顧客企業のマーケティング予算縮小の影響で規模を縮小したり廃業したりするマーケティングサービスの会社も多かったのです。
こうしたリセッションは過去に何度となく起こっていますが、景気が回復すると再び職を得ることが出来ました。今回、様子が異なるのは、リストラされた人の仕事をAIが担当していることです。こうなると景気が回復しても復帰する仕事はもうありません。メール配信やランディングページ作成、フォームの加工、レポートの作成などはほとんどAIが担当しています。
私の友人のスコット・ブリンカー氏が作成したマーケティングランドスケープは、現在15,000以上のツールがありますが、ほぼ全てにAIが実装されています。AIの普及が進み、マーケティングの世界は大きく変わっています。
4. MOpsから時代はRevOpsへ
テクノロジーの急速な進展により、組織は大きな変革期を迎えています。マーケティングオペレーション(MOps)からレベニューオペレーション(RevOps)への移行が加速しており、部門間の連携(アラインメント)だけでは不十分となりました。
各部門が独自のツールを使用することでサイロ化が進み、これを解消するためにレベニューオペレーションへの統合が進みました。チーフレベニューオフィサー(CRO)がマーケティング、セールス、カスタマーサクセスを統括し、CEOにレポートする体制がトレンドになっています。多くのグローバル企業がこのモデルを採用し、成功を収め始めています。
5. 原点回帰が始まっている
AIの登場により、マーケティングの原点回帰が進んでいます。
オペレーショナルな仕事はAIが担うため、人間はより上流の「戦略」を担うようになっています。誰に何をどうやって販売するか、という大きな問いは変数が極めて多いので、未だ人の仕事なのです。
マーケティングの基本は「正しい人に、正しい情報を、正しいタイミングで提供する」という「3R(Right person,Right information,Right timing)」です。その前提から戦略立案を考えるときに外せないのが、フィリップ・コトラーのSTP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)フレームワークで、これが再評価されています。
しかし、日本企業は製品やサービスを膨大に持っているという理由で、STPを苦手としています。多くの商材でSTPをしていないので、それは「誰がターゲットですか?」という質問にすら明確な答えが返ってきません。その解決策の一つとして我々が提案しているのが、「価値の定義(DoV:Definition of Value)」のディスカッションです。お客様があなたの会社、製品、サービスを選ぶ理由は何なのか、ということをディスカッションするセッションです。この価値を再定義して、その価値を求めているセグメントを探すためにSTPを行うなら、そう難しくなくターゲットを定義出来るのです。
6. ICPについて
ICP(Ideal Customer Profile)は、この5年ほどでアメリカやヨーロッパのカンファレンスで多く聞くようになった言葉で、「理想的な顧客プロファイル」と訳します。単純に自社の製品やサービスを買ってくれそうなお客様、あるいは今自社の製品/サービスを買ってくれているお客様ということではなく、自社の製品やサービスで劇的に生産性や業績を向上させる顧客を定義することが重要です。
前述のDoV(価値の定義)とICPは鍵と鍵穴の関係にあり、これを明確にすることでマーケティングのエッジが鋭くなり、成果に繋がりやすいと考えています。
高い効果を出すためには、ナレッジが重要なポイントになります。これがないとフレームワークやツールを活用できないため、ナレッジの習得を日々心掛けてください。