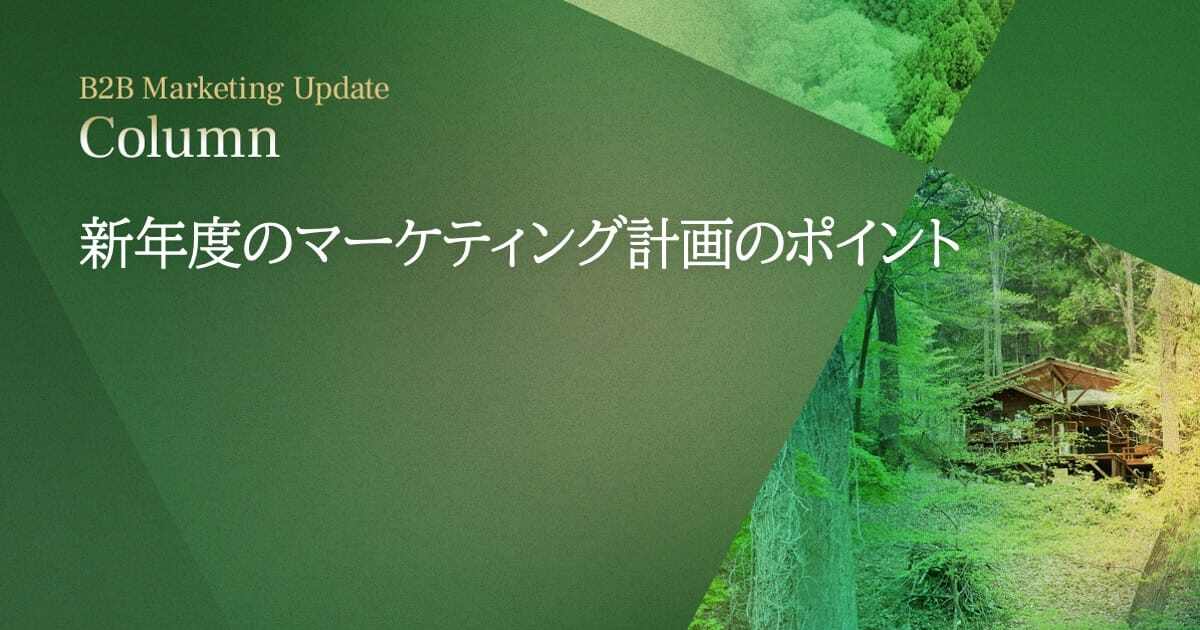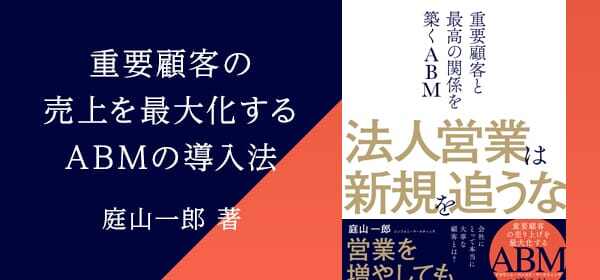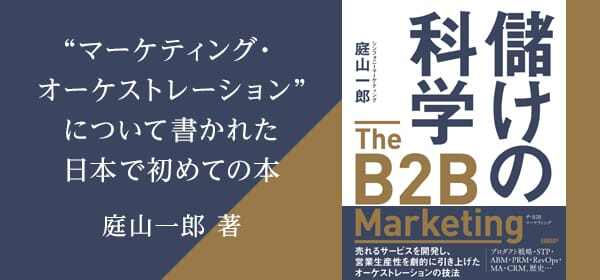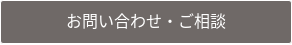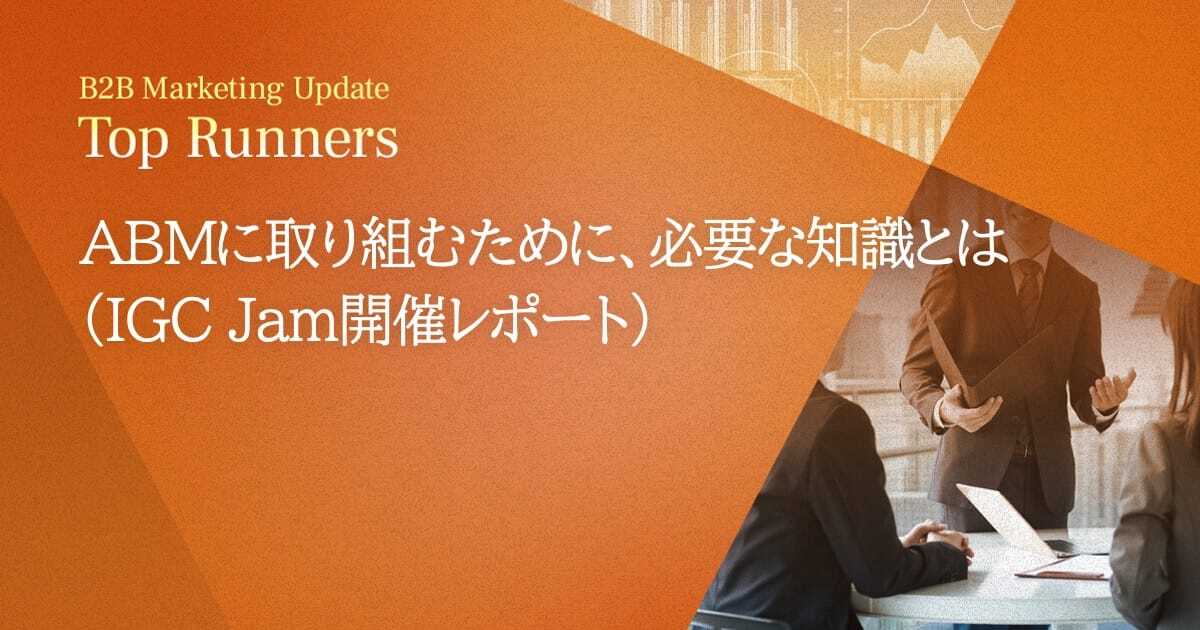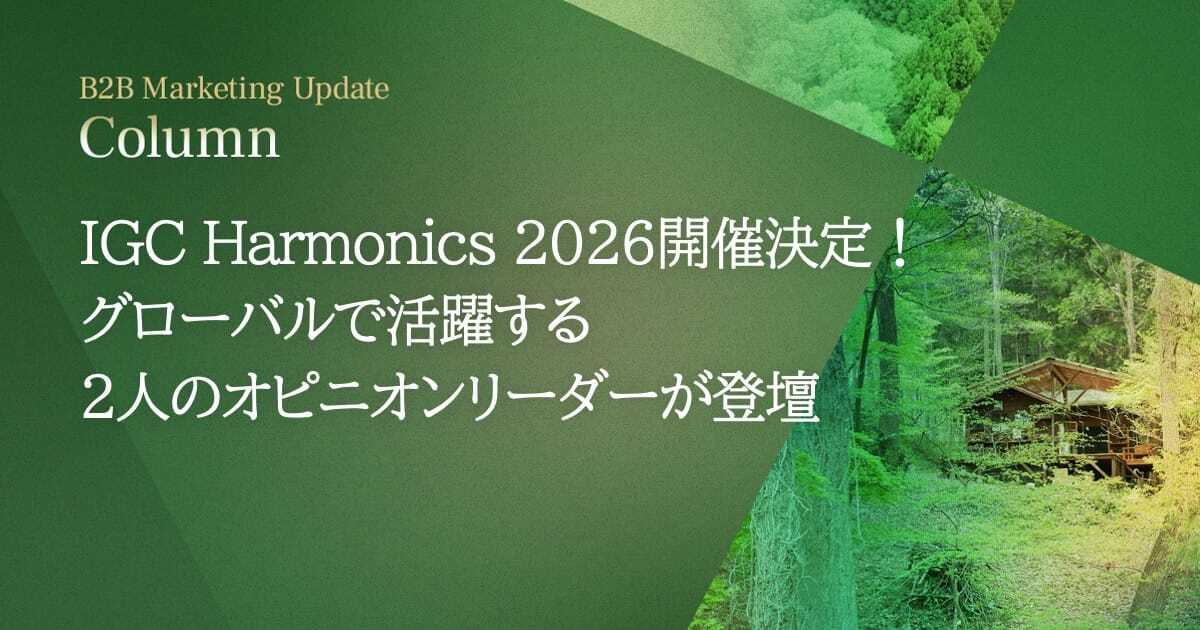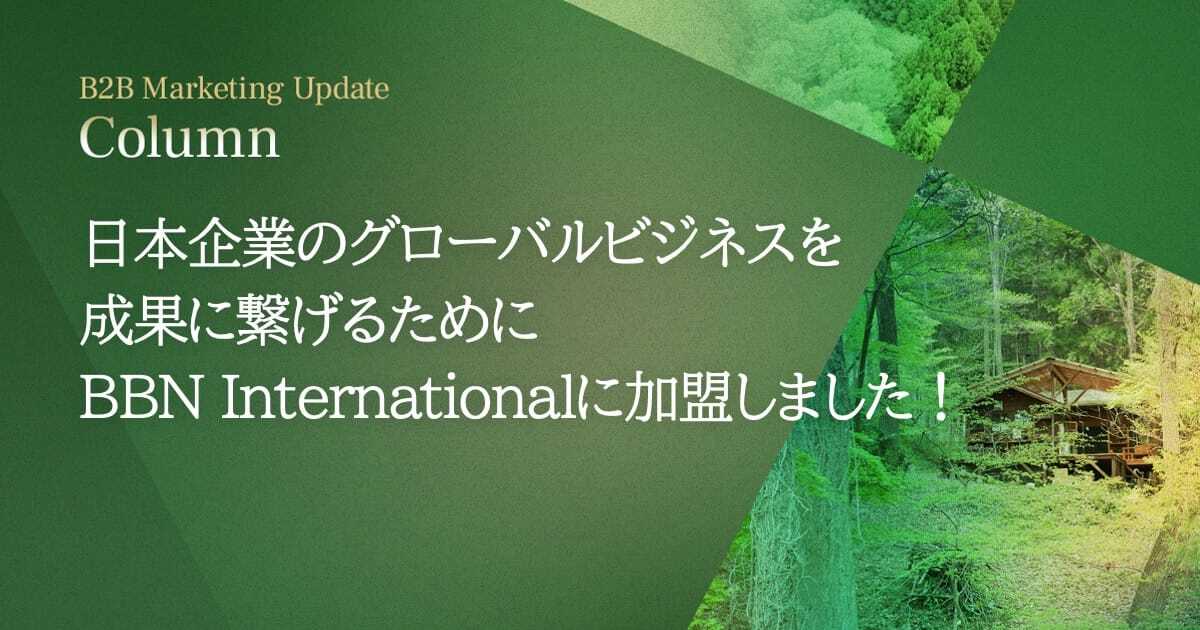多くの企業が新年度を迎える4月。今年のマーケティングプランを立てる方も多いかと思います。
今回は、変化の激しい環境下で成果につなげるためのマーケティングプランニングをするポイントを解説します。
経営戦略のサブ戦略
私がアドバイザリーとして企業の上層部の方などにお話するのは、マーケティング戦略は経営戦略を実現するためのサブ戦略でなければならないということです。
多くの企業には経営戦略は存在します。CEOが書く中期経営計画がそれです。しかし人事から財務、コンプライアンスなど経営全般を書く経営戦略には、それを実現するための具体的なサブ戦略が必要です。そのマーケティングの部分の詳細を書いたものがマーケティング戦略で、基本的にはCMOが書きます。
CMOというポジションがいない多くの日本企業では、それぞれの事業部や製品担当者がバラバラにマーケティング戦略を作ってしまいます。この個別最適のマーケティング戦略と、経営戦略の間に、本来は経営戦略との整合性を踏まえた全体最適なマーケティング戦略が存在しなければなりません。
戦略の間違いを戦術でカバーすることはできないように、事業部だけ、製品だけのことを考えたマーケティングプランでは経営戦略に貢献できません。
まずは、自分たちのマーケティング戦略が経営戦略のサブ戦略として、整合性が確保されているか?正しい戦略のもとマーケティングの実行計画が立てられているのか、を俯瞰的に確認することが重要です。
IT部門が関与せずに導入できるクラウドタイプのマーケティングツールが増えたことの副作用で、バラバラな戦略、バラバラなツールでのいくつものサイロができてしまいました。そのため、それぞれのオーナーが既得権を主張するのは統合データ管理すらできない企業が多くなりました。これは今後ABMに取り組みたい企業にとっては大きな障害になります。
日本企業はCMOかそれに類する権限を持った役職を置き、全体最適なマーケティング戦略を描き、それを実現するための組織とテクノロジーの改編を始めるタイミングです。
定量目標の重要性
マーケティング部門を創り、MAを導入して数年経つ企業が増えてきました。最初のころは、DX推進の一環としてシステム投資に寛容だった会社もそろそろ売上げ貢献を求められる頃です。しかし現実は多くのマーケティング部門はメールを配信するだけ、電話を掛けるだけ、デジタルマーケティングを実施するだけで終わっています。
私は、マーケティングは売上に貢献しなければ意味が無いと考えています。そのためには、自分たちが事業や営業プロセスに対して、どのように貢献するのかを、数字的に計画を立て、そのプランをいつでも報告できることが重要だと考えます。
パーセンテージではなく実数で、出来れば「円」か「ドル」で設計し、それを実現するための実行計画を立て、成果を可視化しながらPDCAを回し、継続的にマーケティングを改善していくことが重要なのです。そして、成果が出ないものは「やめる」判断をし、費用対効果の高い活動にマーケティング予算を投入する判断をするべきなのです。
「去年もやっていたから、今年もやる」という判断からは今年こそ卒業すべきです。
AIツール時代のマーケターに求められるスキル
先日の海外カンファレンスの報告セミナーでもお話しましたが、北米のB2Bマーケティングカンファレスは、AI一色と言えるものでした。もちろんABMもGTMもICPも重要なテーマですが、そのすべてにAIが活用されています。
これからマーケターの仕事も大きく変わっていくことは間違いありません。特にオペレーショナルな仕事はAIに変わっていくため、マーケターとして生き残れるのは、正しい戦略を立て、AIを使いこなせるマーケターだけでしょう。かつて、インターネットの普及が世界を一変させたように、今はAIが世界を塗り替えています。
生き残る鍵は「原点回帰」です。マーケターとしての基礎となる古典的なフレームワークや理論、例えば、STPやホールプロダクト、PPMなどを理解し実務で使えるスキルを付ける。そして、それを基礎として新しい概念であるICPやフレームワークであるABMをキャッチアップし活用していくことが重要です。
そういう意味では、本質的なマーケティング力が一層求められる1年になるでしょう。