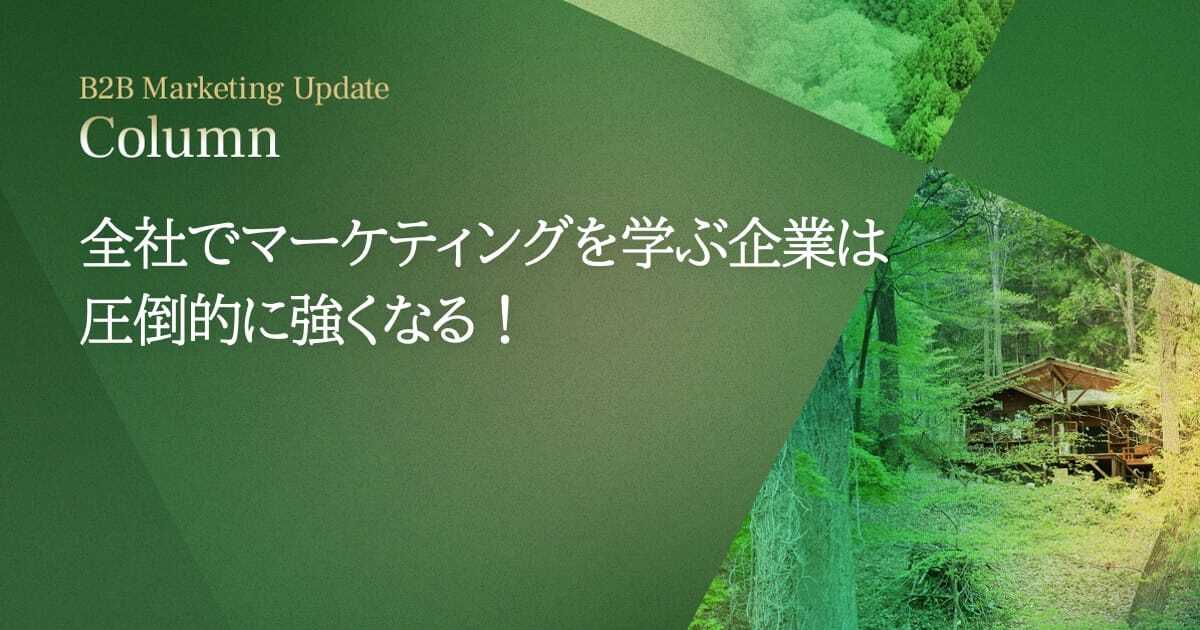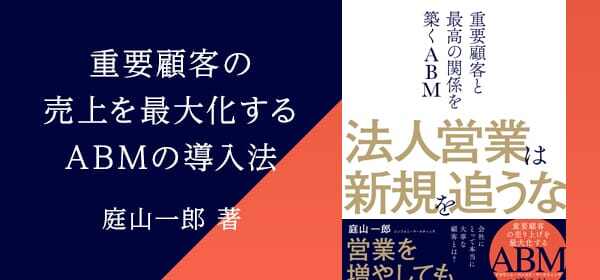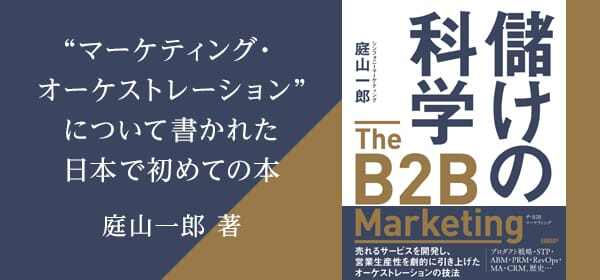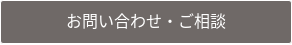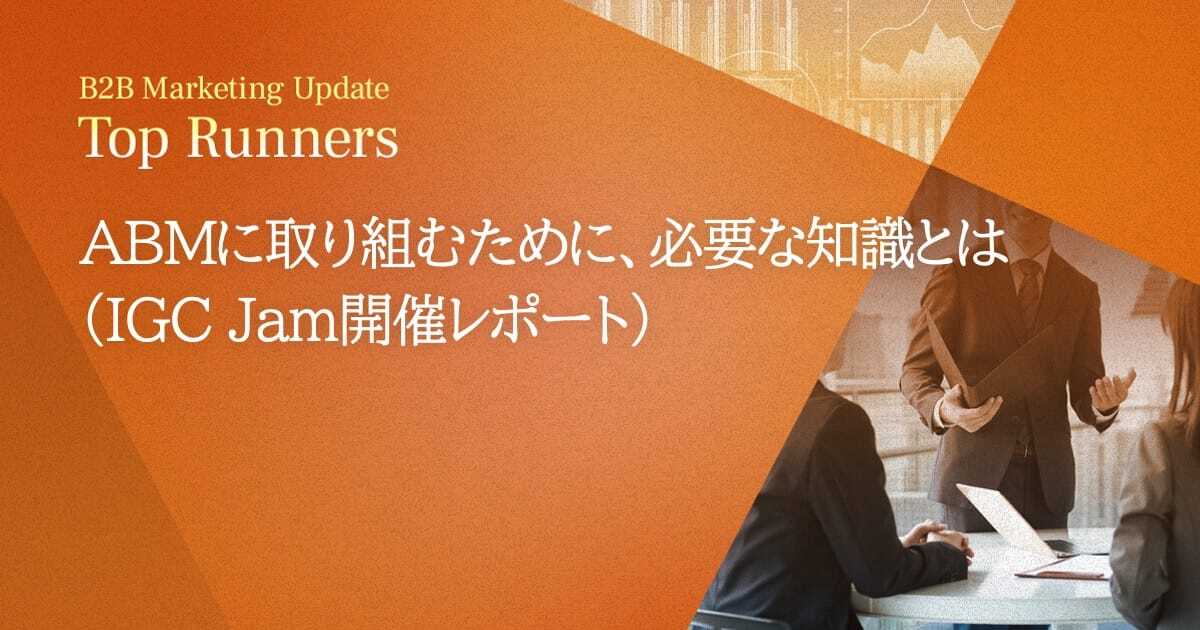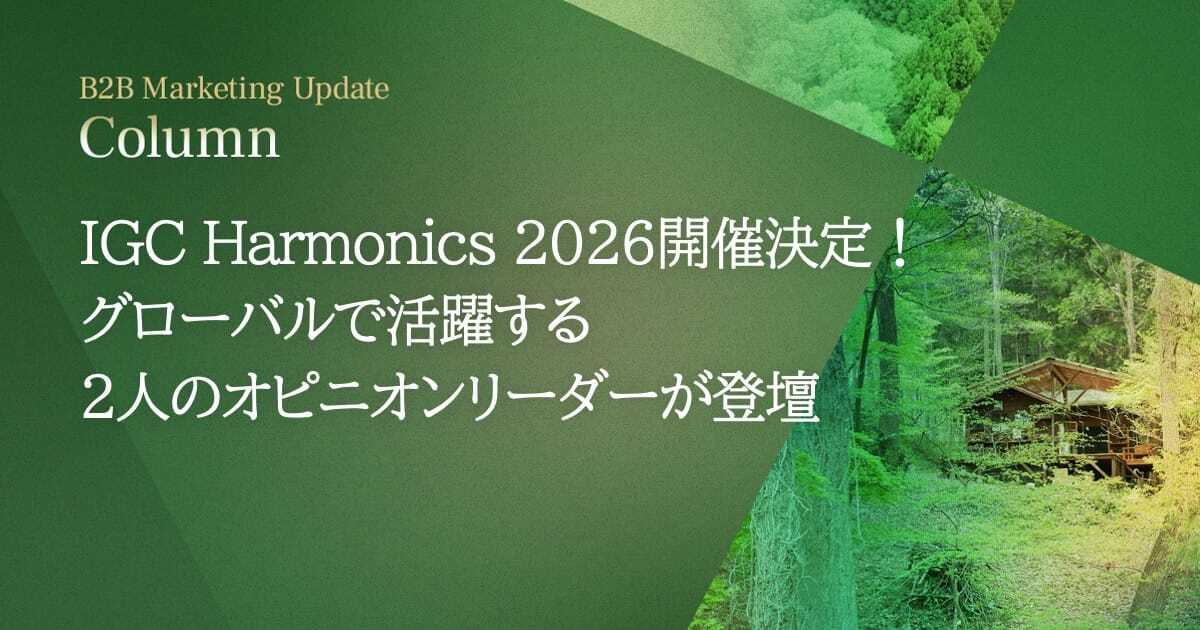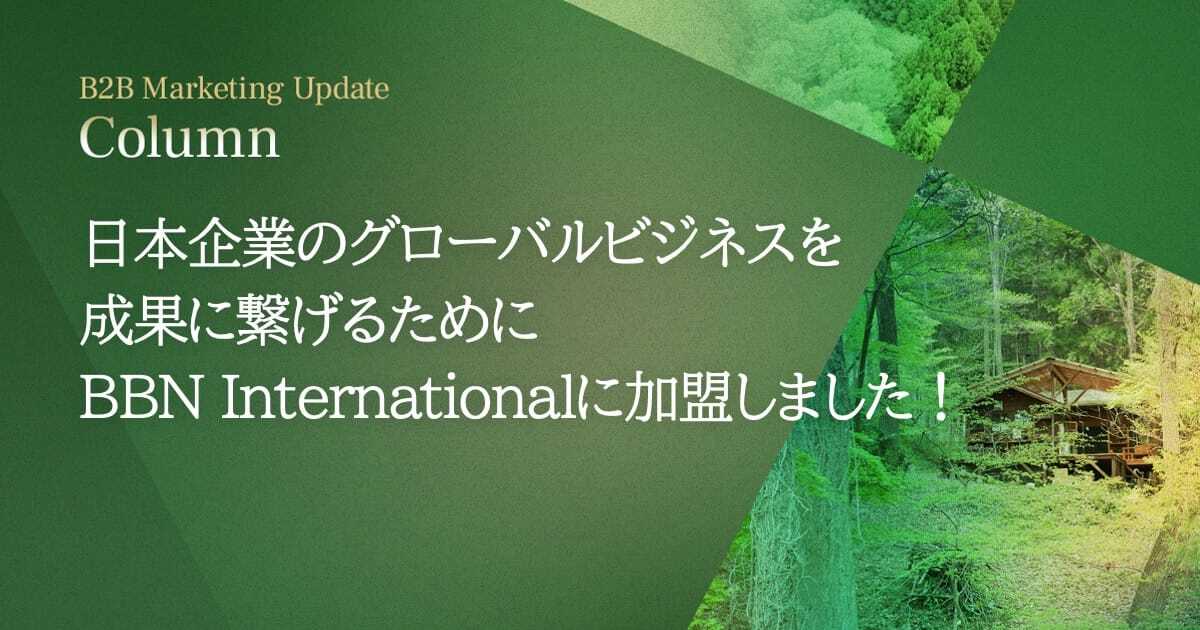今年(2025年)3月に米国に出張した際に、米国のパートナーとのアポイントがあったので、シンフォニーマーケティングが提供しているマーケティング基礎研修受講者の所属部門別の集計データを出してもらいました。話のネタになると思ったのです。
データを見て驚いたのは、マーケティング基礎研修の受講者の60%が既にマーケティング以外の部門だったことです。営業部門が最も多く、他にものづくり(研究開発・設計・生産技術)や広報もいるので、マーケティング部門は既に30%ほどになっていました。
うかつな事に私はこの数字を予想していませんでした。
「どうしてこうなったの?」
と担当者に質問してみました。答えはこうでした。
最初はマーケティング部門やその配属予定者がマーケティング基礎研修を受講してくれます、日本のB2B企業のマーケティング部門の人たちです。
そして受講した後で「この研修を営業部門やものづくり部門も受講したら共通言語が出来て、社内コミュニケーションがとてもやりやすくなるのではないか?」と考えるらしいのです。
会社に帰ってそれを上司に相談すると、多くの企業は研修予算を持っています。受講した人の強い推薦はインパクトが有るので、他部門にマーケティング基礎研修を紹介することになります。実は営業部門やものづくり部門にもマーケティングを学んでみたいと思っている人は潜在的にたくさんいますから、その人たちが手を上げてくれます。そして受講した人がさらに社内で「あの研修は面白い、自社の製品でやるから役に立つよ。目からウロコが落ちるよ」と広めてくれているらしいのです。
他事業部の営業も顧客接点が多い技術営業も、そんな研修があるなら受講したい、となってこの数字になったのだということでした。
そして、営業部門やものづくり部門の受講者が増えた企業には明らかな変化が見られたのです。
特にマーケティング部門と営業部門のコミュニケーションが活性化すると、それらがWebコンテンツ、セミナー、展示会の選定会議などにも反映されます。さらに複数部門やサービスを組み合わせた顧客視点を持った提案ができるようになり、その結果、新規顧客の開拓や、既存顧客へのクロスセルの深堀りなどに成果を出しているということでした。
マーケティングという言葉はとても曖昧に使われていて、ビジネスが混乱するひとつの原因なのです。ですから私は実務の中では出来るだけ「マーケティング」という言葉ではなく「デマンドジェネレーション」とか「ABM」というより具体的な言葉を使うようにしています。
先端技術や市場のシェアを調べるリサーチや、宣伝・広告部門が担当し認知度を上げる目的で行われるブランディングに比べると、商談を見つけ出してそれを営業部門や販売代理店に供給するデマンドジェネレーションや、それを特定の顧客に対して集中的に実施するABMは、営業部門にとって実践するのに理解しやすく、成果を出しやすいのです。
またデマンドジェネレーションを実施している企業の営業部門のマーケティング偏差値が向上すれば、
「だったらこのコンテンツでは欲しい商談は見つからないよ、こっちのケースに替えよう」
という営業とマーケティングの前向きで効果的な連携が生まれるのです。
シンフォニーマーケティングの基礎研修のシラバスにはSTP(Segmentation、Targeting、Positioning)が入っています。営業部門やものづくり部門の人たちがSTPの概念を理解して使えるようになると会議の内容が見違えるように変化するのを私は何度も見ています。
さらには、営業がマーケティングを学んだ事で「マーケティング部門で仕事がしてみたい」という異動希望が出てきたり、逆に全社横軸のマーケティング部門から、ある事業や製品の専属でマーケティングをやりたいというプロダクトマーケティング希望者が出てきたりして、社内の人事交流が活発にもなるようです。
私はこうした社内の人事交流や、連携が企業を強くし、マーケティング力を向上させると信じています。
シンフォニーマーケティングは営業部門やものづくり部門が机を並べて、マーケティングを学ぶことで、日本のB2B企業の「売る力」の向上を目指しています。