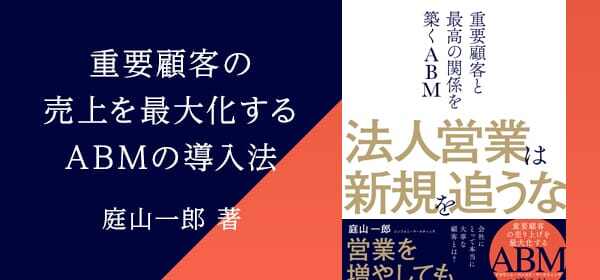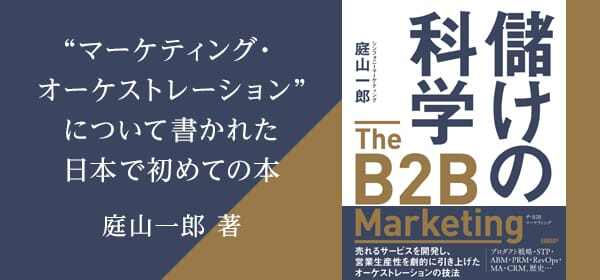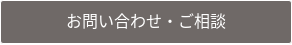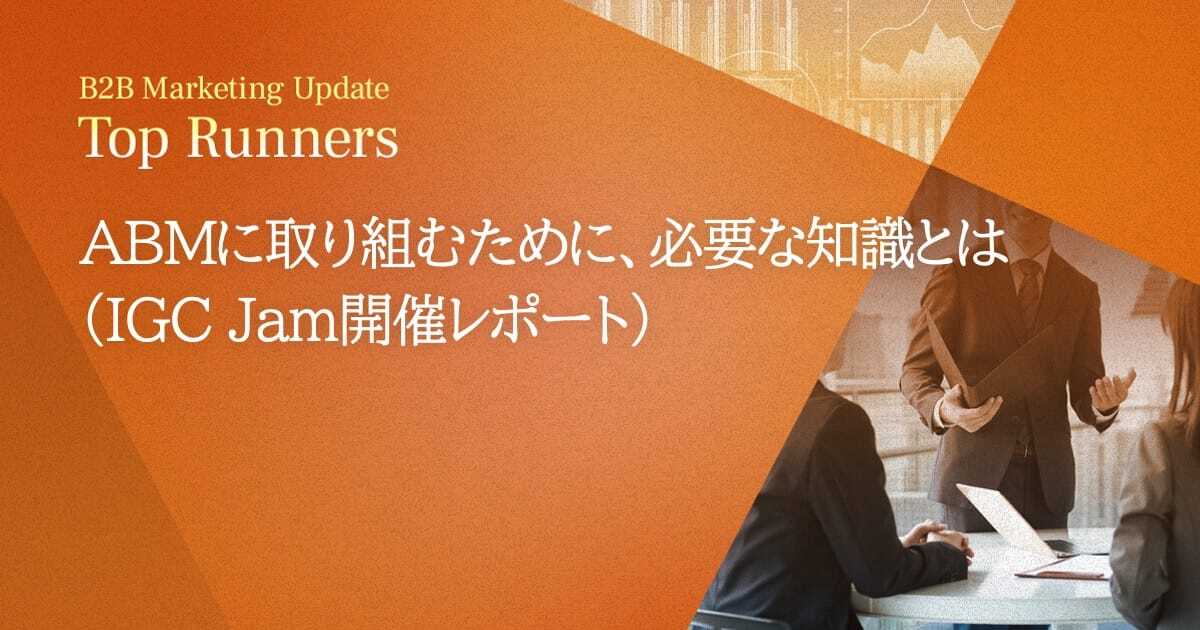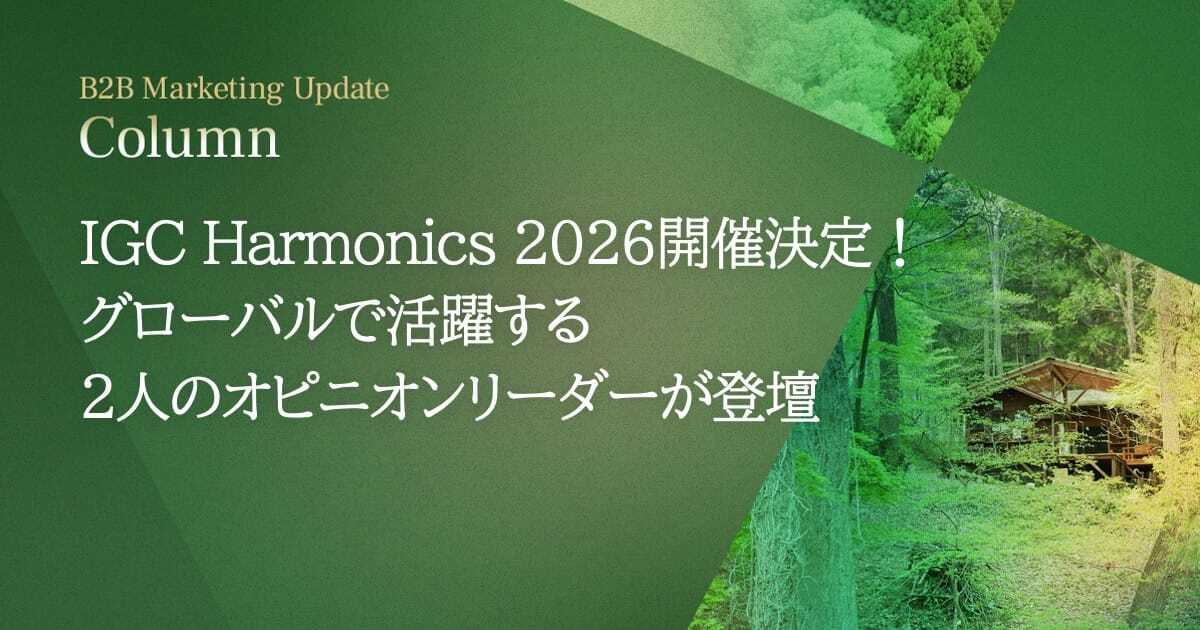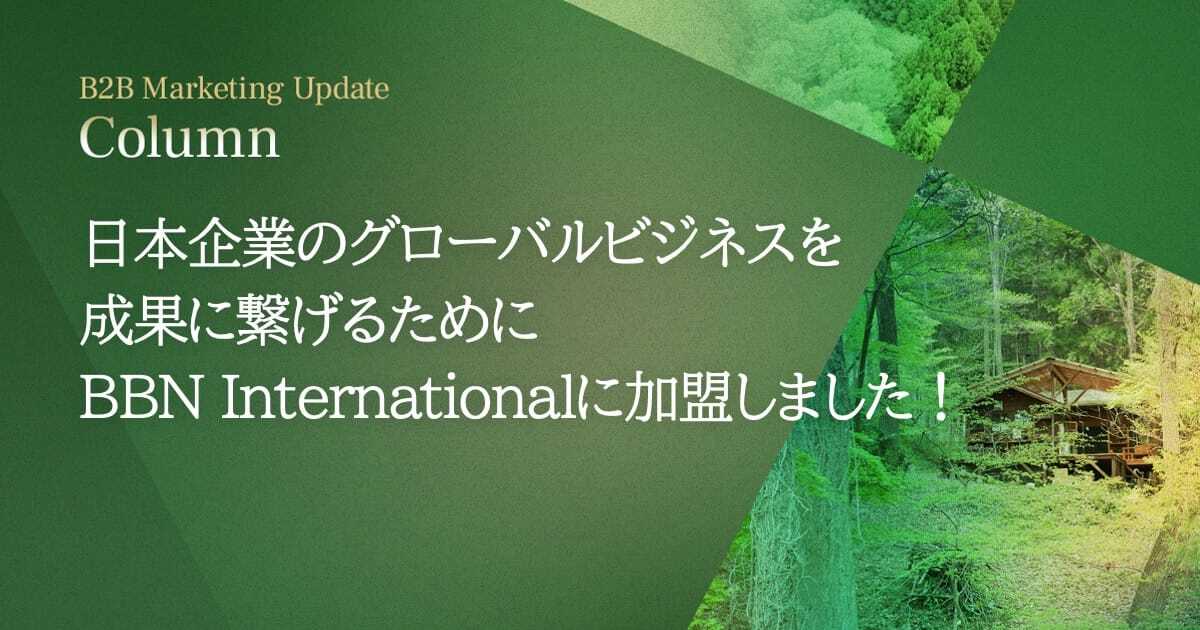ABM(アカウント・ベースド・マーケティング)は、近年B2Bマーケティング関係者の間で注目を集めるマーケティング戦略となっています。しかし、その本質を理解することは、特に日本市場ではまだ障壁が多いようです。Top Runners、今回はこのABMについて、グローバルの最新情報やその基本的な考え方、実践のポイントを解説します。複数の米国テクノロジー企業でCMOを歴任してきたB2Bマーケティングのスペシャリストで、日本初登壇となったRandi Barshack 氏のIGC Harmonics 2024 Day2の講演から振り返ります。
ABMは比較的新しい概念であり、2016年ころに初めてマーケティングの世界に登場しました。それ以前は、マーケティングテクノロジーの選択肢が限られていたため、ABMのような手法は存在していませんでした。しかし、近年のテクノロジーの進化に伴い、ABMは急速に発展し、現在では多くのB2B企業が採用しています。例えば、アメリカのB2B企業の約70%がABMを活用しており、これは世界的なマーケティングのトレンドとなっています。一方、日本ではABMの普及はまだ進んでおらず、ABMベンダーが日本に進出していないという現状もあります。

Randi Barshack 氏
Randi Barshack 氏は「ABMは買うものではなく、やるものだ」と強調しています。つまり、ABMは特定のソリューションやツールを購入することによって実践するものではなく、企業が持つリソースやデータを活用して取り組むべきマーケティング戦略だということです。実際に、ABMを始めるためには大規模な投資は必要なく、現状のリソースを活用してスタートすることが可能です。また、ABMは単なるマーケティング戦略ではなく、セールスとマーケティングが連携して取り組むべき「アプローチ」であることも重要なポイントです。
ABMに関してよくある誤解の1つに「ABMは大企業向けの手法である」というものがあります。しかし、ABMは企業規模に関係なく適用可能です。また、「ABMは最重要アカウントにのみ適用される」といった考え方も間違いです。ABMは、特定のアカウントに焦点を当てることで、より効果的なマーケティングとセールスを実現するための戦略であり、その適用範囲は広いのです。

Randi Barshack 氏
ABMを始める際には、まずアカウントを特定し、データを活用して優先順位を付けることが重要です。AIやデータ分析ツールを活用することで、ターゲットアカウントリスト(TAL)を作成し、どのアカウントにリソースを集中させるべきかを明確にできます。また、フィット(適合性)、エンゲージメント(関与度)、インテント(意向)の3つの要素を基に、アカウントを分類し、それぞれに適した戦略を立てることが求められます。
Randi Barshack 氏は、日本企業が持つファーストパーティーデータの活用の可能性に注目しています。理由として、日本では多くの企業が顧客情報や名刺データを蓄積しており、これらを活用することでABMを効果的に実践できる可能性があるからです。また、日本市場に特化したABM戦略を構築することで、他国とは異なる独自の成果を上げることも期待されます。
ABMを成功させるためには、小さなステップから始めることを推奨しています。例えば、1つのセールスチームや特定のアカウントからスタートし、その成果を基に徐々にスケールを拡大していく方法が効果的です。また、ABMは一度実施して終わりではなく、常に改良と反復を続けるプロセスであることを理解することも重要です。
「ABMは、単なるツールの導入ではなく、企業のマーケティングとセールスの連携を深め、顧客との関係を強化するための『やり方』です。日本市場においても、ABMを試みることで新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。まずは小さな一歩を踏み出し、そのプロセスを楽しむことを忘れないでください」とRandi Barshack 氏。
最後に「ABMは買うことではありません。ABMはやるものです」という言葉で講演を締めくくりました。
IGCサービスご利用の企業様は、コンテンツライブラリの「IGC Harmonics」カテゴリーで、具体的な事例も交えたRandi Barshack 氏の講演をノーカット版(日本語字幕付き)でご覧いただけます。この機会に、ぜひご覧になってください。