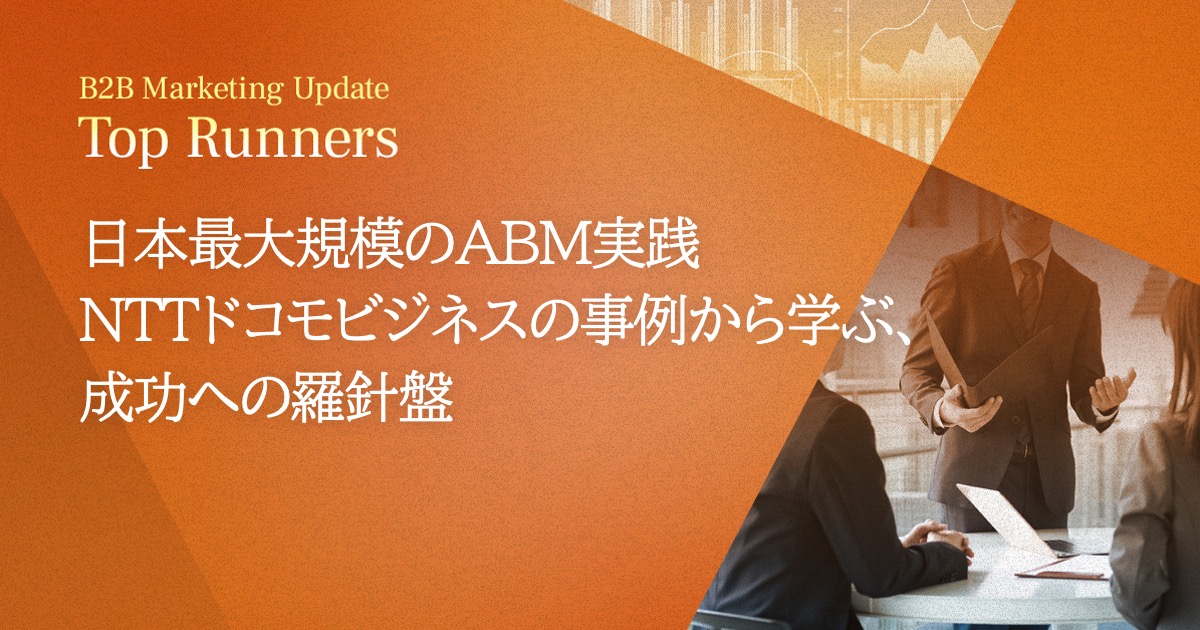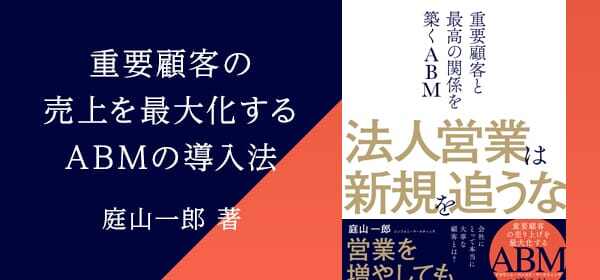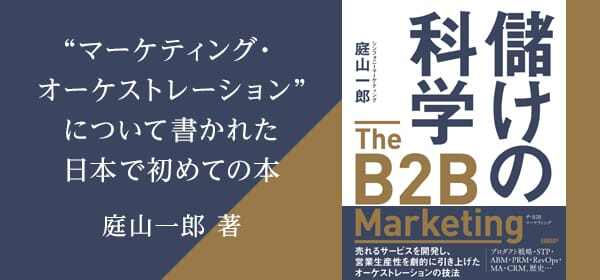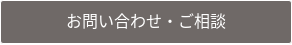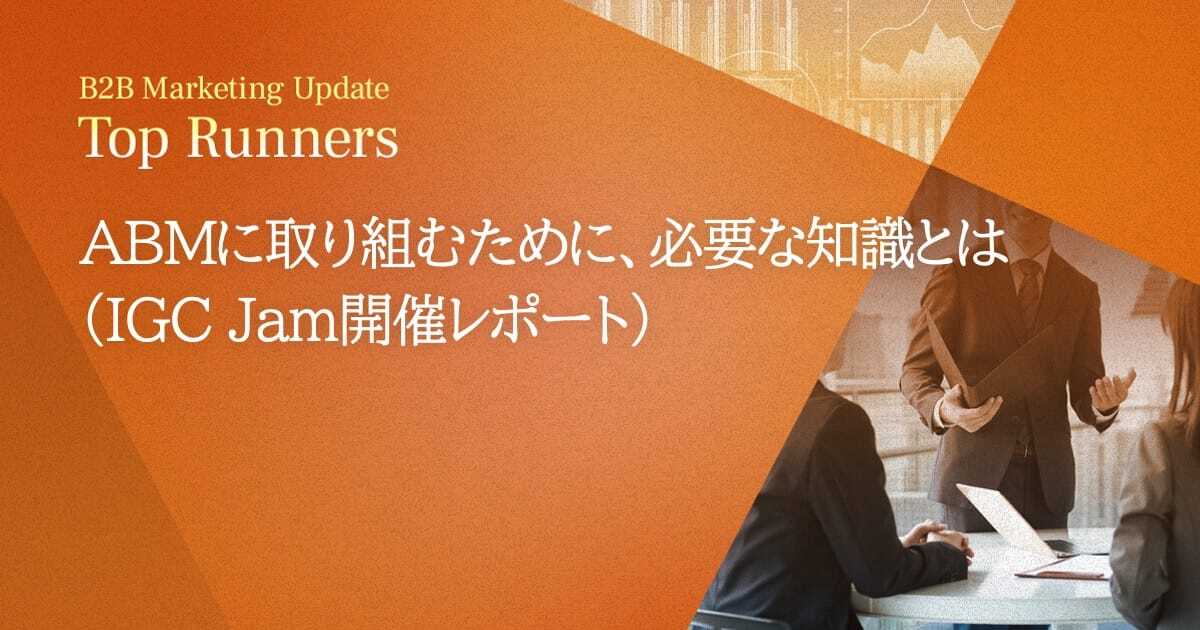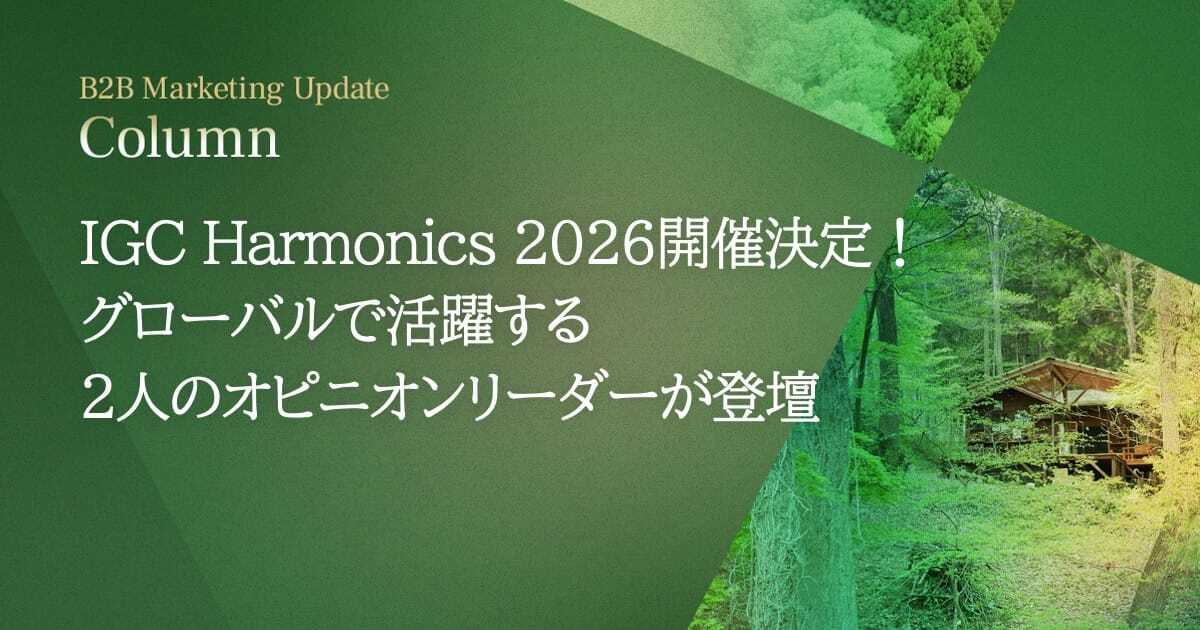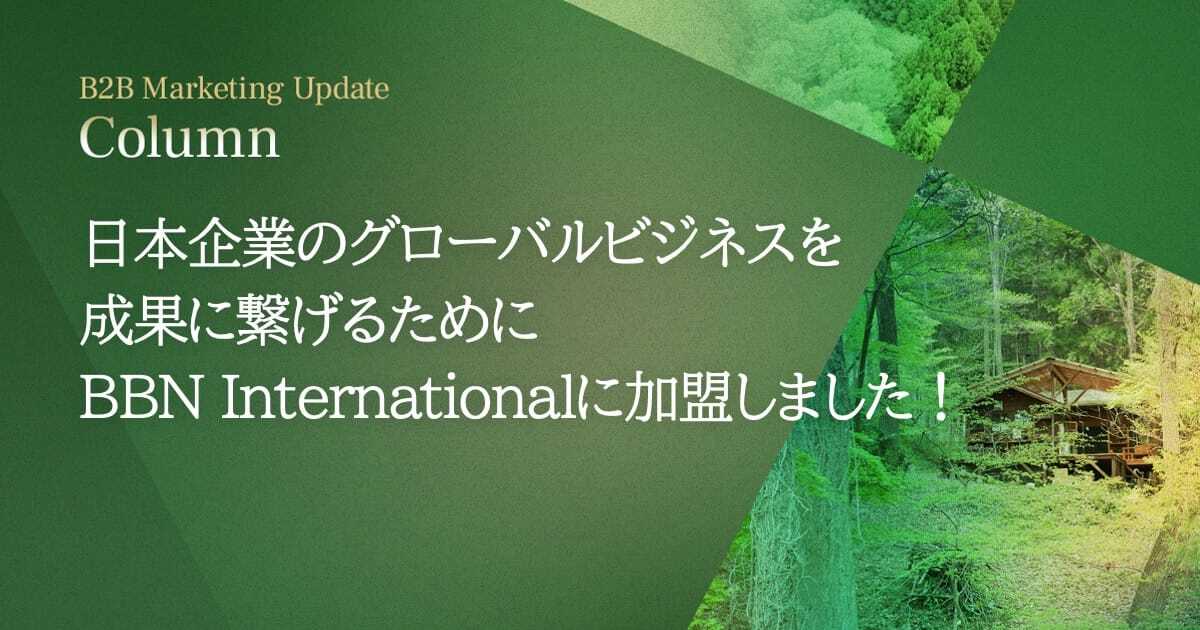多くのB2B企業様が「ABM(アカウント・ベースド・マーケティング)にどう取り組むべきか」という課題に直面する中、日本最大規模のABMを実践し、大きな成果を上げている企業があります。それが、NTTドコモビジネス株式会社です。
Top Runners今回は、ABMを成功に導くための本質的な考え方と具体的な勘所について、同社でB2Bマーケティングを統括されている戸松正剛氏に庭山がインタビューした内容を紹介いたします。
経営戦略の実現へ。ABMを「ABX」と捉える視点
弊社ではABMを「特定重要顧客と最良の関係を築くことで、強い顧客基盤を構築し、収益を最大化することを目的とした全社的なマーケティング戦略」と再定義しました。一方、戸松氏は「ABX」という考えを提唱されています。これは、グローバルの潮流を知る前に、ご自身で考え抜いた末に辿り着いたそうで、その「X」には二つの重要な意味が込められていると語ります。
“当社の「X」の1つは「Experience」、もう1つは「Everything」です。今、当社のセールスのトップ(副社長)はCMOやCROではなく、CCXO(Chief Customer Experience Officer)であり、マーケティング・セールスの重要な方針として掲げているのがCX(Customer Experience)なんです。CXが収益の源泉という考えなので、それを実現するためのABXであるという大義です。
もう1つは、そのプロセス上の話です。(中略) 例えば情報システム部や人事部などもアカウントに向かうワンコンポーネントだと思っていて、そういう意味で「Everything」にもこだわっています。”
(お客様インタビューから抜粋)
マーケティングは「横糸」。全社を巻き込むチームセリングの実践
庭山が著書でも述べている「マーケティングは横の糸になる」という考え方に、戸松氏は深く共感されたと言います。なぜなら、特定の業界や顧客と長年向き合うアカウント営業、いわば「縦糸」だけでは、組織全体の力を顧客に届けることはできないからです。そこで、経営戦略という最も太い横糸に併走する形で、マーケティングが「横糸」としての役割を担う。戸松氏はこのマーケティング組織の立ち位置を、経営とフロント営業の間という意味で「1.5列目」と表現されています。
この「横糸」としての役割を具現化しているのが、事業共創の場である「OPEN HUB」です。ここは、ターゲット顧客の上位20%をお招きするための特別な空間であり、お客様の課題解決の触媒となる専門人材「CATALYST(カタリスト)」が約1,100名も在籍しています。お客様の課題に応じて、AIの専門家やエンジニア、デザイナーなど最適なCATALYSTがチームを組み、顧客と向き合う。これは、本来バックヤードにいる人材の専門性をも顧客のために活かす仕組みであり、One to OneのABMを対面で実践する場なのです。
成功の礎はデータにあり。千載一遇の好機を活かしたデータ基盤改革
これほど壮大なABMを実践するためには、何よりもまず「データの綺麗さ」が不可欠であると戸松様は強調します。7年前に今の会社にジョインした当初、マーケティングツールは導入されていたものの、データは部署ごとに分断され、同じお客様が別々に登録されているなど、決して綺麗な状態ではなかったそうです。この根深い課題を解決する転機となったのが、グループ統合という大規模な組織再編でした。
“大掛かりなカスタマイズがされていたCRMも見直しを行い、基本の状態に戻してシステムをすべて見直しました。(中略) ABMを進めていくのなら、精神論ではなく情報システムレベルでしっかり構築していく必要がありますし、データマネジメントがひとつの転機にもなりました。”
(お客様インタビューから抜粋)
最後に戸松氏は、これからABMを実践する企業へのアドバイスとして、「ABXの『X』に何を当てはめるかが企業の経営戦略そのもの」だと語ります。その変数に何を入れるかを常に考え、ポリティカルパワーを持つ人に理解してもらう努力を惜しまないことが、成功への最低限の条件だと強調しています。
NTTドコモビジネスの取り組みは、今後、自社でABMを推進するうえでも大変参考になる事例だと考えています。この機会にぜひ、このインタビュー記事をご覧ください。