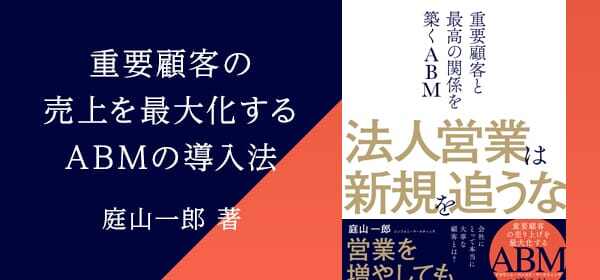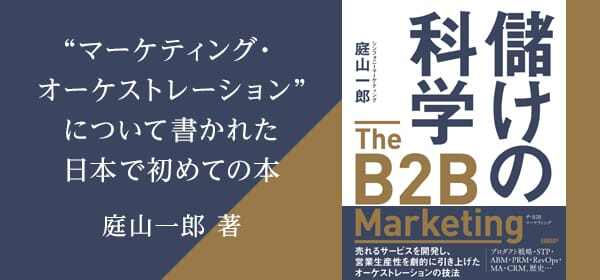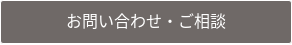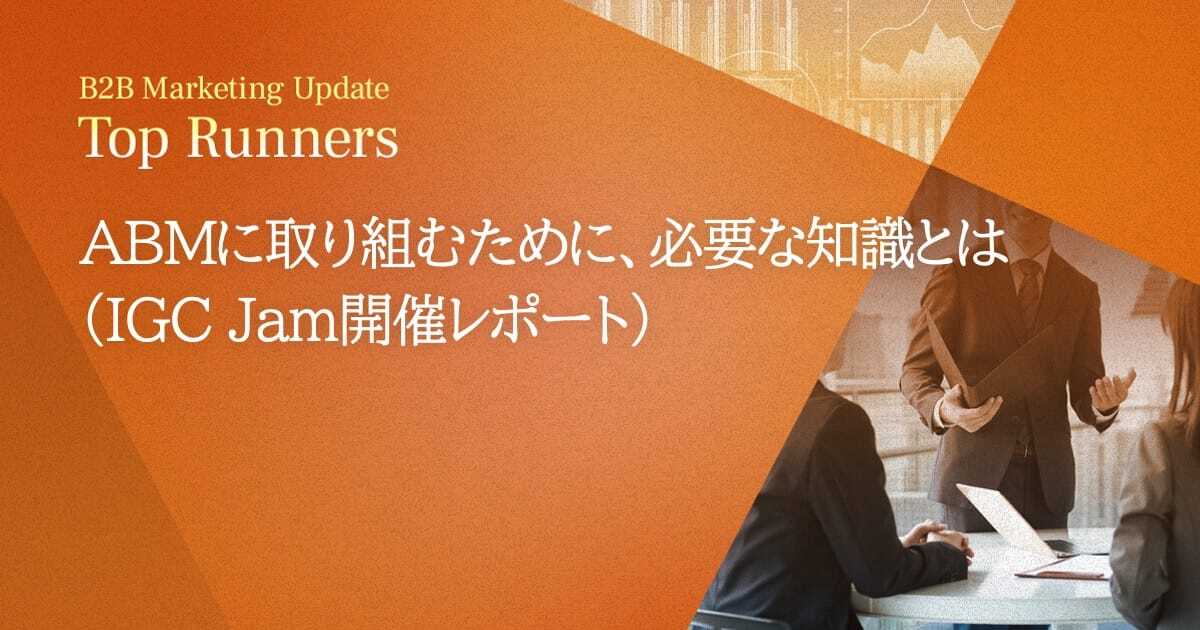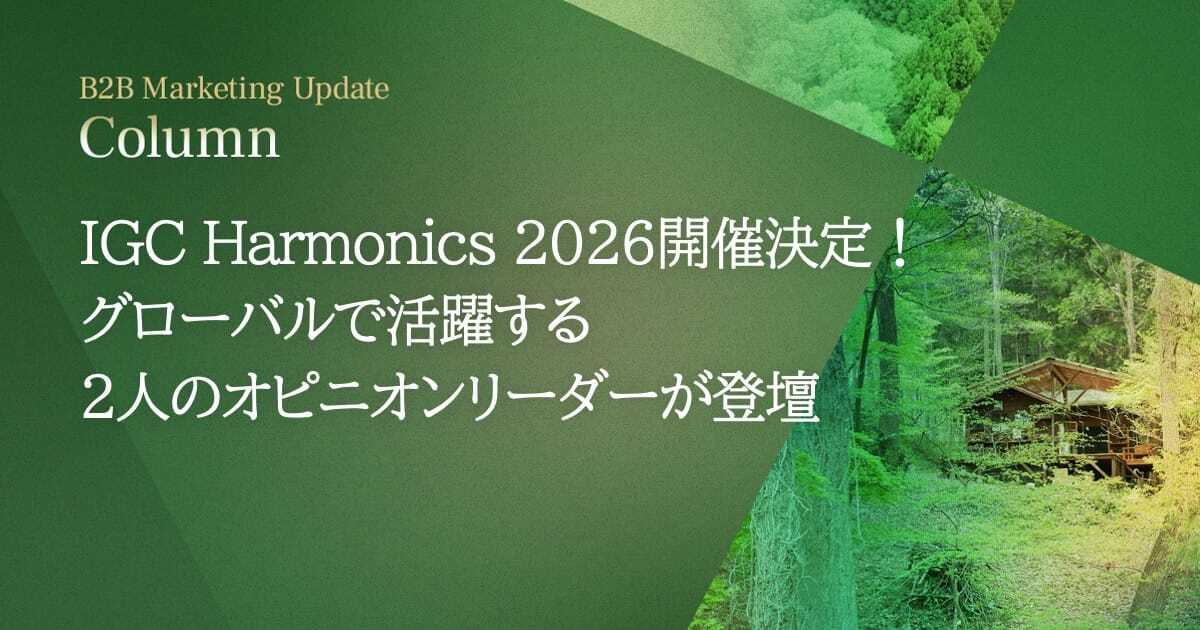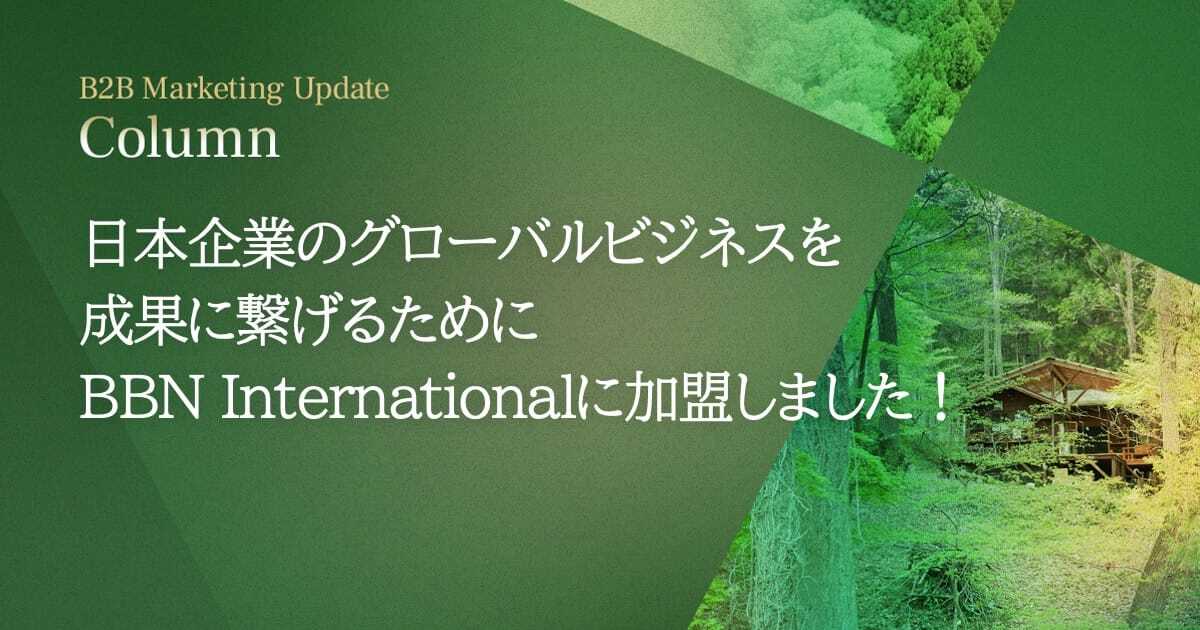以前MOPD(マーケティング オーガナイジング パラドックス:Marketing Organizing Paradox)のことを書きました。マーケティング部門が存在しなかった日本のB2B企業がマーケティング部門を創設し、MAを導入して、マーケティング活動を始めると、投資をして予算を使いはじめます。ところが、当然すぐには受注に貢献できず、また営業との連携(アラインメント)が不十分だと貢献できているかどうか測定できないことから「ROMI(マーケティング投資利益率:Return On Marketing Investment)」の物差しを当てられると最低の結果になってしまうことです。
さらに営業部門や広報部門との軋轢を引き起こし、経営幹部からは「いつになったら受注に貢献するんだ」とプレッシャーを掛けられ、にっちもさっちも行かない状態になっている企業が多いのです。
これを放置するとマーケティング部門の解体や、営業の下部組織への組織改編、部門縮小、キーパーソンの離職などといった問題を引き起こし、その企業は「マーケティング」へのトラウマを抱えることになり、やがて機能不全に陥ります。
実は、2015年以降にマーケティングに取り組んだ多くの日本のエンタープライズB2B企業がこの状態か、その予備軍です。
MAを導入し、SFA/CRMも入っていて、Webもリニューアル、出展する展示会も増やし、名刺デジタル化ツールも導入、しかしそれらは繋がっておらず、データも整理整頓されておらず、今の状態を可視化もできない、という状態なのです。
この状態から一刻も早く抜け出さなければなりません。
その特効薬は「原点回帰」です。
MAの操作やメール配信などはオペレーションであって戦略ではありません。AIはオペレーションを効率化しますが、戦略を立てるのは人間の仕事です。
「誰に何をどうやって売るのか?」
弊社でとても大事にしている原則にイゴールアンゾフが提唱した「3S」があります。
3Sとは、何かの課題を解決する時には先ず戦略(Strategy)を立てなさい。次にその戦略を実現するために充分な質と量を備えた組織(Structure)を創りなさい。そして「何を実現したいのか(戦略)」と、「誰が実施するのか(組織)」を要件定義にしてシステム(System)を選択しなさい、という事です。
残念ながら多くの日本企業はこの逆です。先ず流行に乗ってシステムを導入します。そして後から慌てて組織を創るか、既存の組織に割り当てます。その組織は戦略に基づいて設計されたものではありませんから、何をするにも「帯に短し、たすきに長し」の状態です。そして肝心のマーケティング戦略は存在しません。「組織は戦略に導かれる」とはアルフレッド・チャンドラーの言葉ですが、多くの日本企業には導かれるべき戦略が存在しないのです。
マーケティング戦略とはCEOが書いた経営戦略を実現するための最も重要なサブ戦略です。責任者はCMOです。CMOがいない日本企業にはマーケティング戦略が無いケースが多いのです。
マーケティング戦略の最上流のところは自由度と変数が多過ぎてAIの仕事ではありません。ここに人間の役割が在ります。そしてここのスキルを磨けるのはマーケティングの古典なのです。
数年前から米国や欧州のB2Bマーケティングカンファレンスでは古典的なマーケティングの話題が多くなりました。元々これらの古典的なフレームワークを使っていた弊社にとっては「我が意を得たり」という感じなのです。
レジス・マッケンナの「顧客リレーションシップ」、フィリップ・コトラーの「STP」、エベレット・ロジャースの「イノベータ理論」、セオドア・レビットの「ホールプロダクト」、クレイトン・クリステンセンの「イノベーションのジレンマ」、デビッド・アーカーの「ブランド論」などのマーケティングの古典とも言える人達の言葉やフレームワークが再び脚光を浴びています。明確に原点回帰が起こっているのです。
日本企業もMAやCDPの操作や導入などばかりにリソースを費やすのではなく、自社や自社事業のマーケティング戦略を点検し、無ければ創る、足りなければ見直すという作業に取りかかる時だと私は考えています。