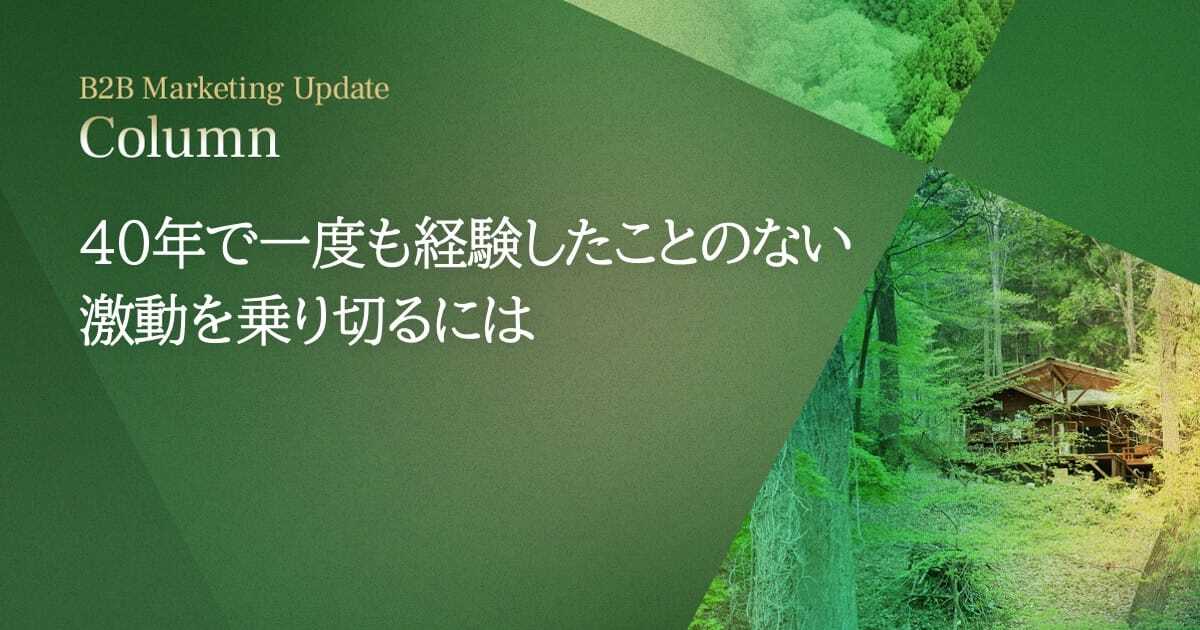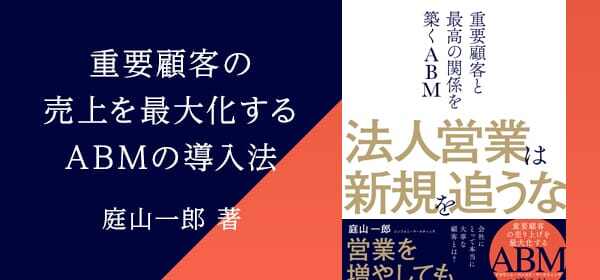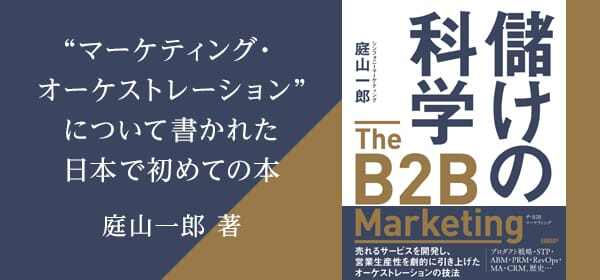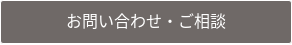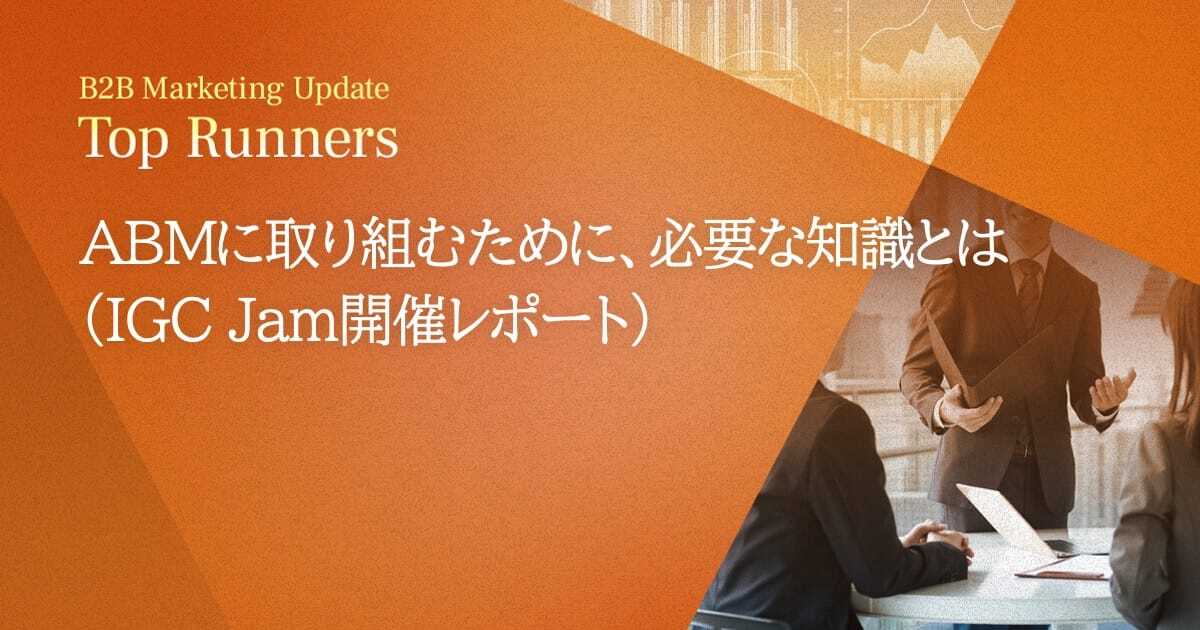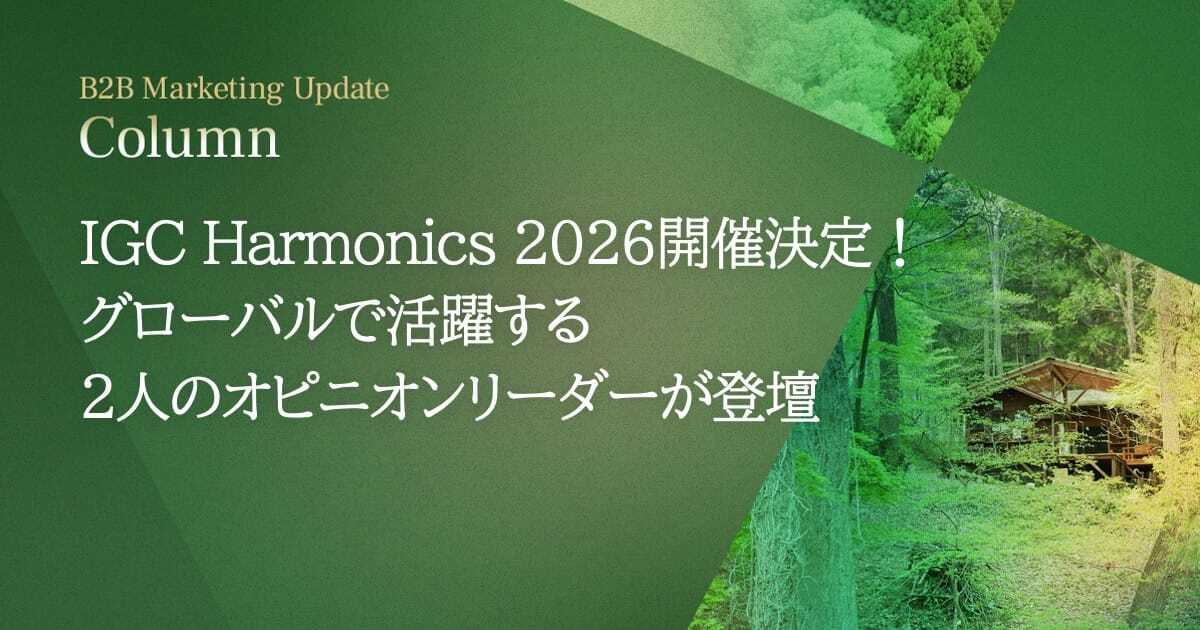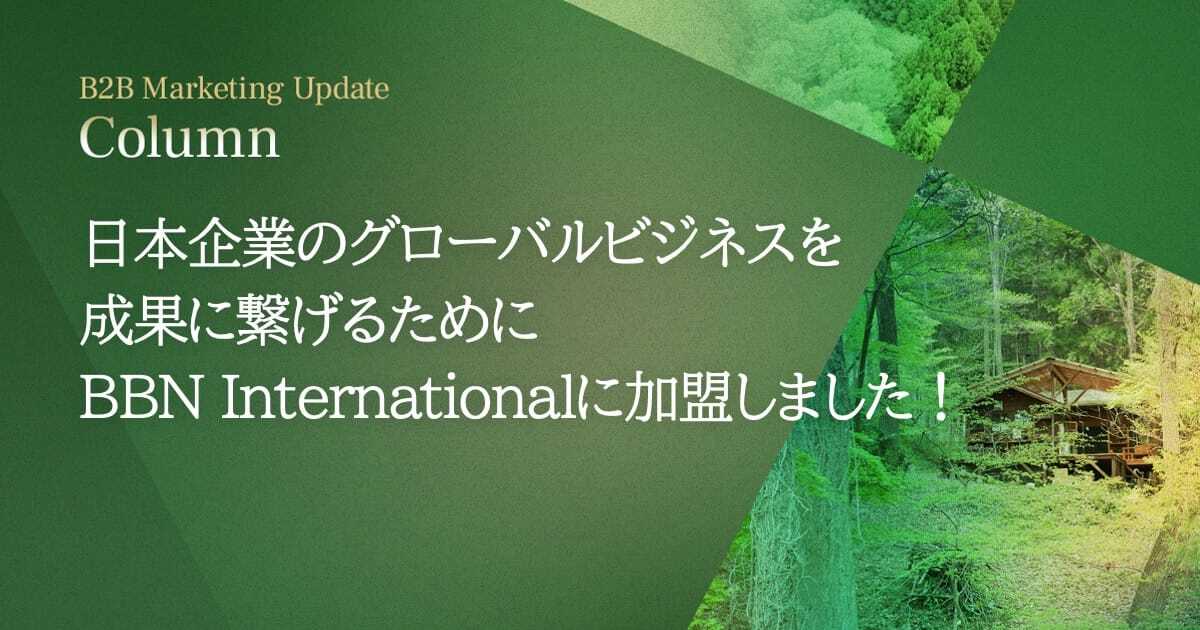私は、18歳の秋に大学の図書館でT・レビット博士の本を手に取り、それに収録されていた「マーケティング近視眼」を読んだその時にマーケティングを一生の仕事にしようと決めました。以来40年以上をマーケティング一筋でキャリアを積んできましたが、私の経験の中でも今ほど変化の激しい時代はありません。
変化はチャンスと言いますが、そうだとしたら今ほどチャンスに溢れた時代はなく、同時に全く先の読めない時代も経験がないのです。

約40年前の庭山 一郎
私はマーケティングサービスの会社を経営しています。それで今まであまり言わなかったことがあります。それは日本企業の内製化指向への疑問です。まず自分たちでやってみよう、誰かに相談する前に自分たちで考え、やってみよう、という日本企業に多く見られる思考回路はある面とても大事で良いことでもありますが、時間とリソースを膨大に無駄にしている側面も確かにあるのです。
弊社は2000年に世界最初のMA(マーケティングオートメーション)であるカナダ生まれのEloquaが米国向けにリリースされた時から、Eloquaユーザーの日本法人のサポートをしてきました。それはMarketoやSilverpopでも同じで、そういう意味では弊社は日本でのMAの普及に大きく関わった企業でもあります。
2025年現在、日本では20,000社を超える企業がMAを導入しています。しかし、未だに多くの導入企業がメール配信機能だけしか使っていないのです。
マーケティングのナレッジが十分ではない企業がMAを導入しても出来る事はメール配信までです。それでは受注に貢献することは出来ません。MAはマーケティングのツールですから、使いこなすにはB2Bのマーケティングナレッジが必要なのです。MAの中のデータの名寄せや属性情報の付与なども不完全なので、分析しようにも出来ない状態です。これもナレッジの問題です。日本の法人データのマネジメントの難易度は経験した人でないと理解出来ないでしょう。
私は、もうナレッジを後回しにした内製化主義で時間を無駄にすることが許されないと考えています。冒頭に書いた通り、激動の時代に入ったからです。
何が激動なのか?ひとつひとつが解説に長い文を必要としますので、ダイジェストで書きます。
検索の無い世界
ジェネレーティブAIの普及から3年が経って、検索が激減しています。何かを調べるときにAIを使った人はもう検索には戻らないと言われています。弊社のクライアントでもSEO由来のオーガニックは毎月激減しています。 フォレスターリサーチのCEOジョージ・コロニーがオースチンで「検索の無い世界」を語ったのは2年前ですが、それが現実になっています。
相手が電話に出てくれない世界
この10年で、「インサイドセールス」、「BDR」、「ADR」などの様々な呼び方でコールサービスが大きく増えたことで、コールドコールと呼ばれる「ニーズを確認していない対象へのコール」が激増しました。B2Bの場合、当然、最初に電話を取る人は営業が会いたい人ではありません。そのために会いたい本人が電話に出てくれることを弊社では「到達」と呼んでいます。アポイントとは「到達×訪問承諾」なのです。 この「到達率」が激減しています。明らかに掛け過ぎだし、本人に到達するためにスクリプトを工夫した結果「もう騙されない、電話は取り次がないで下さい」という人が増えています。
選定の最終段階まで営業と会わない世界
欧米のいくつかのリサーチ会社のデータですが、「購買担当者(バイヤー・バイインググループ)は選考の最終段階まで営業には会いたくない」という傾向がハッキリしています。この傾向はこの10年同じ方向で数値が増えています。
AIとAIが交渉する世界
エンタープライズB2B企業のWeb訪問者の50%はボット、つまり人間ではないと言われています。現在、これらはスパイボットと呼ばれる意味の無いロボットですから無視していれば良いのですが、ごく近未来はこれらが購買エージェントになります。この際には購買の意思と権限を持ったエージェントですから高くスコアしなくてはなりません。それが出来る体制の準備が急がれています。
顧客を区別する世界
ABMは「重要顧客にフォーカスして取引を最大化しよう」とする戦略です。これは重要顧客とそれ以外を区別することを意味します。日本人的には「お客様を売り上げで差別するのか?」となるかもしれません。でも、年間数十億円を購入してくれる顧客と、数千万円の顧客は区別しなければなりません。なぜならば競合に奪われた時のダメージがまったく違うからです。 こうした本物の戦略的ABMが日本でも始まっています。
こうした激動の時代を生き抜くためには、ナレッジと経験を持つガイドが絶対に必要です。ガイドに求められるのは知識ではなく「経験」なのです。 弊社がアドバイザリーサービスのメニューに力を入れているのはそれが理由なのです。
アドバイザリー活用コラム
アドバイザリーサービスで見つけた「顧客に刺さる」価値提案の作り方