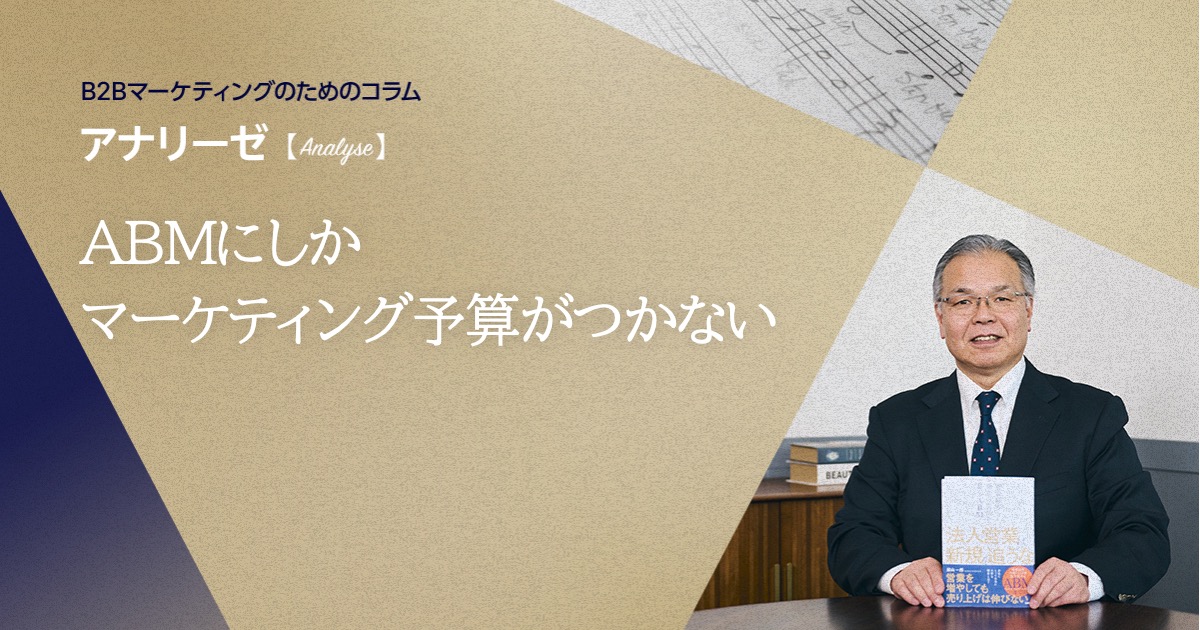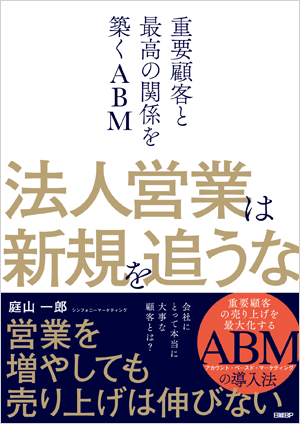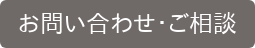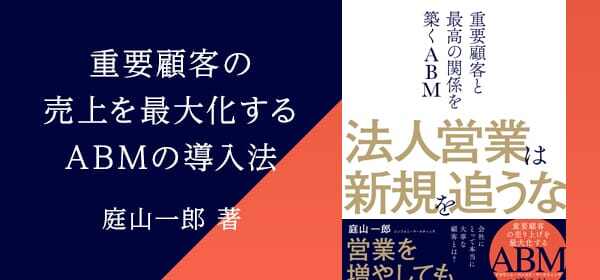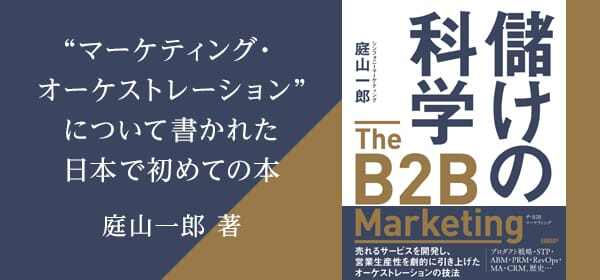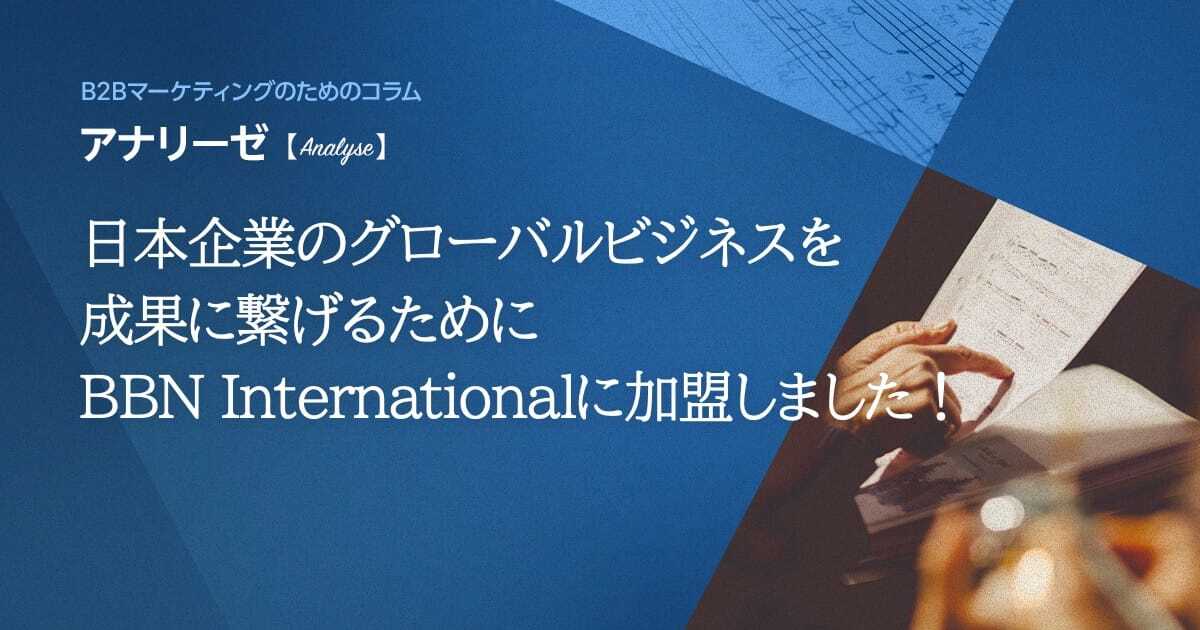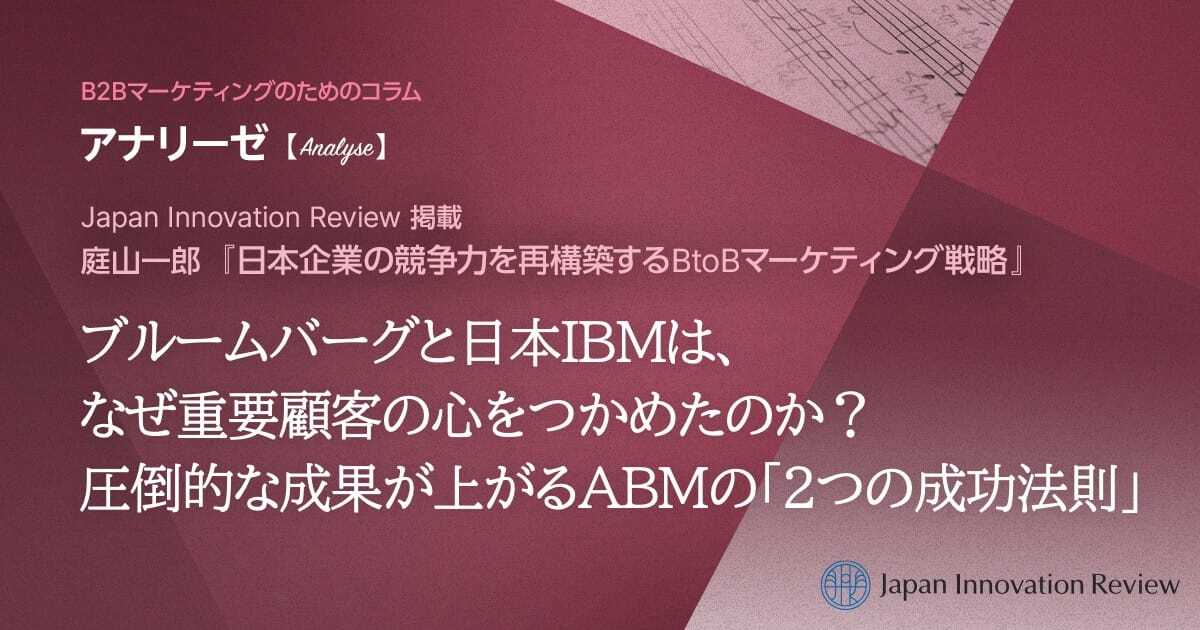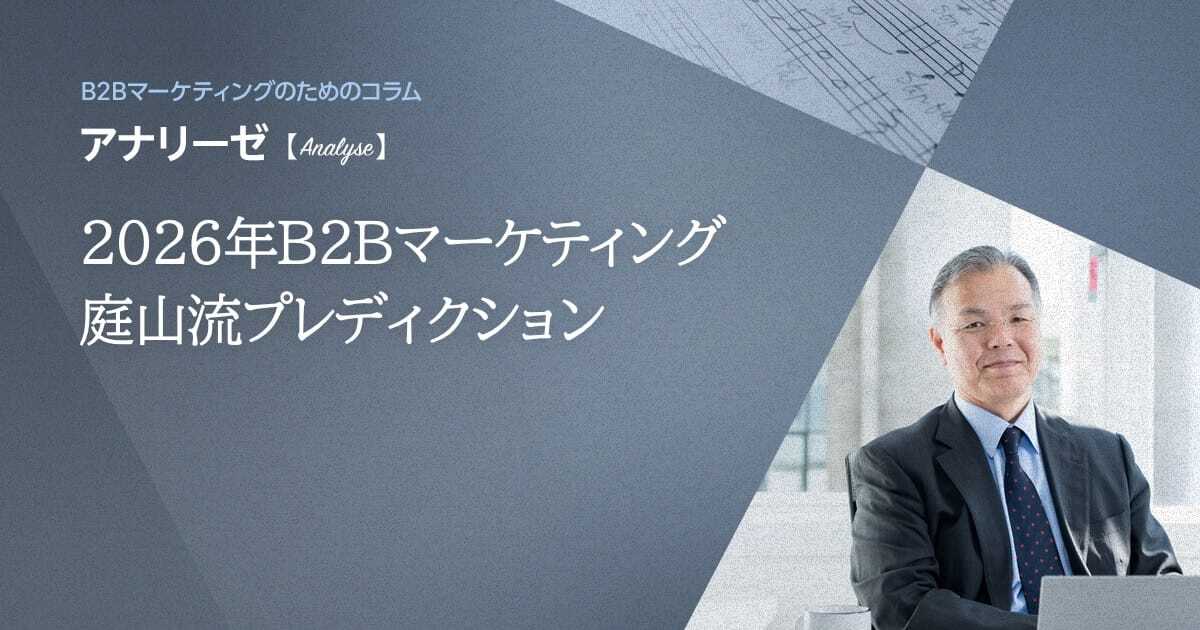「釣った魚に餌はやらぬ」は大きな間違いだった?
ABMが注目される背景にはテクノロジーの進化がありました。顧客管理にCRM(Customer
Relationship Management:顧客関係管理システム)が、案件のパイプラインマネジメントにSFA(Sales Force Automation:案件管理システム)が、そして商談をつくるデマンドジェネレーションにMA(マーケティングオートメーション)が登場したことで、売り上げや利益の構造が可視化されたのです。それと同時に、絶対に守るべき重要顧客が、意外に大切に扱われていなかったことも分かりました。
日本の慣用句に「釣った魚に餌はやらぬ」というものがあります。営業リソースは新規にこそ振り向けるべきで、既存顧客は納品チームが守ればよい、という考え方が長く続いていた中で、テクノロジーの進化によって、それが大きな間違いであり、営業リソースを割り振るべきなのは既存の重要顧客ではないのか、と気付く人が出てきました。
そして、ごく少数の重要顧客に絞ってマーケティング活動を展開したところ、思ってもみない成果が出たのです。さらにABMで関係が強化された重要顧客は売り上げが最大化されるだけでなく、利益でも他の顧客よりはるかに稼げていることが見えてきました。
そして複数の製品やサービスを納品すればするほど、顧客から見たら重要なベンダーとなり、さらにシナジーを効かせた提案ができるようになって顧客との関係は深くなりました。こうした実績に基づいて、ABMは全社戦略となり、グローバル企業では世界規模で展開されるようになったのです。
私の会社が2022年度以降に国内の外資系企業からいただいたご相談は、勉強会や壁打ちのアドバイザリー、実施計画の策定からプロジェクトマネジメントまでのほぼ100%がABM関連です。外資系企業では、ABMに関連したマーケティング施策以外では予算が承認されない、という状況にまでなっています。
出典:法人営業は新規を追うな 重要顧客と最高の関係を築くABM 庭山一郎著(日経BP)より