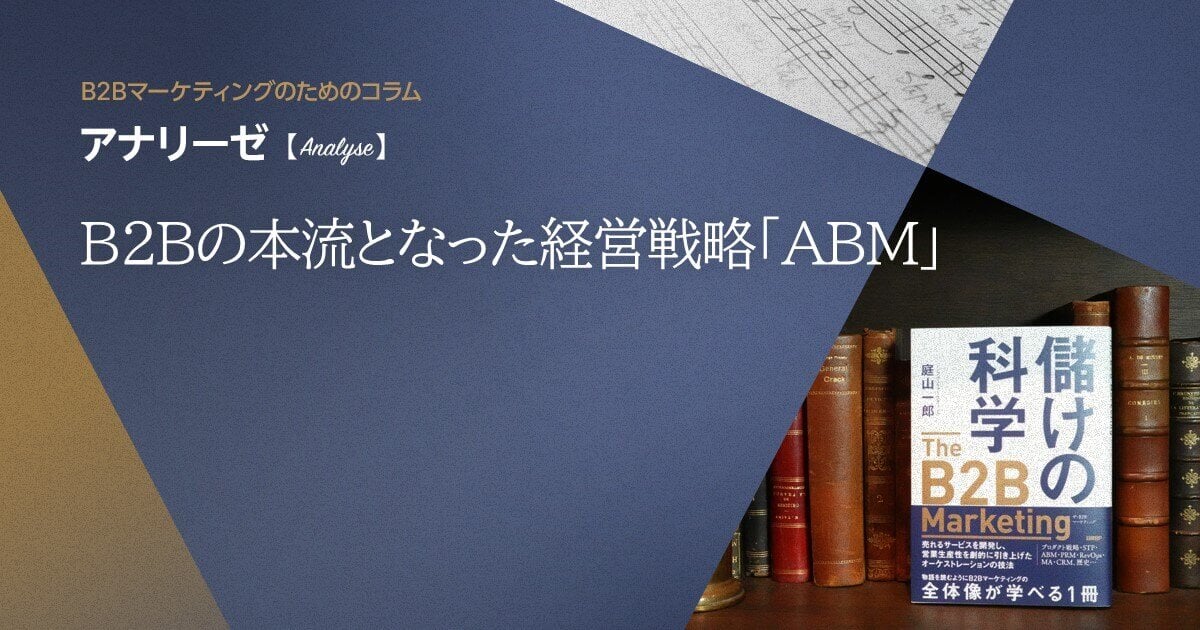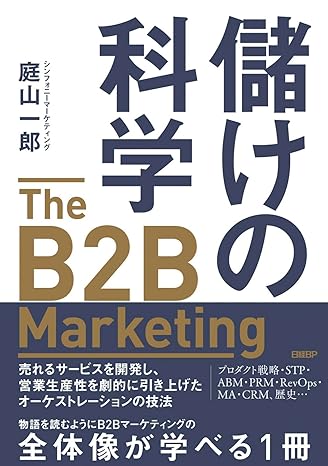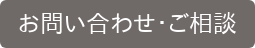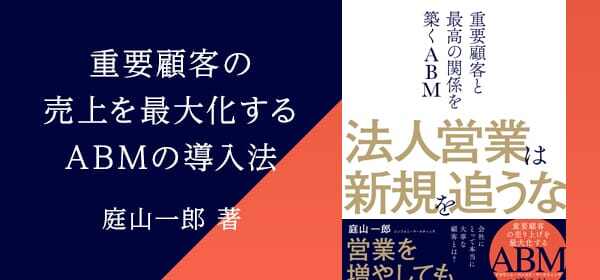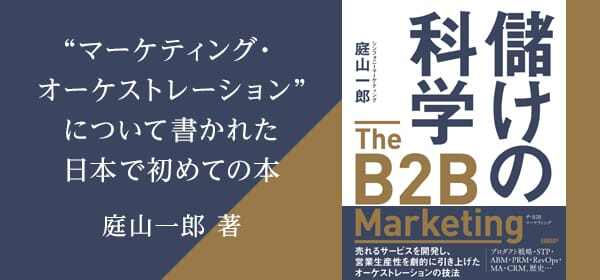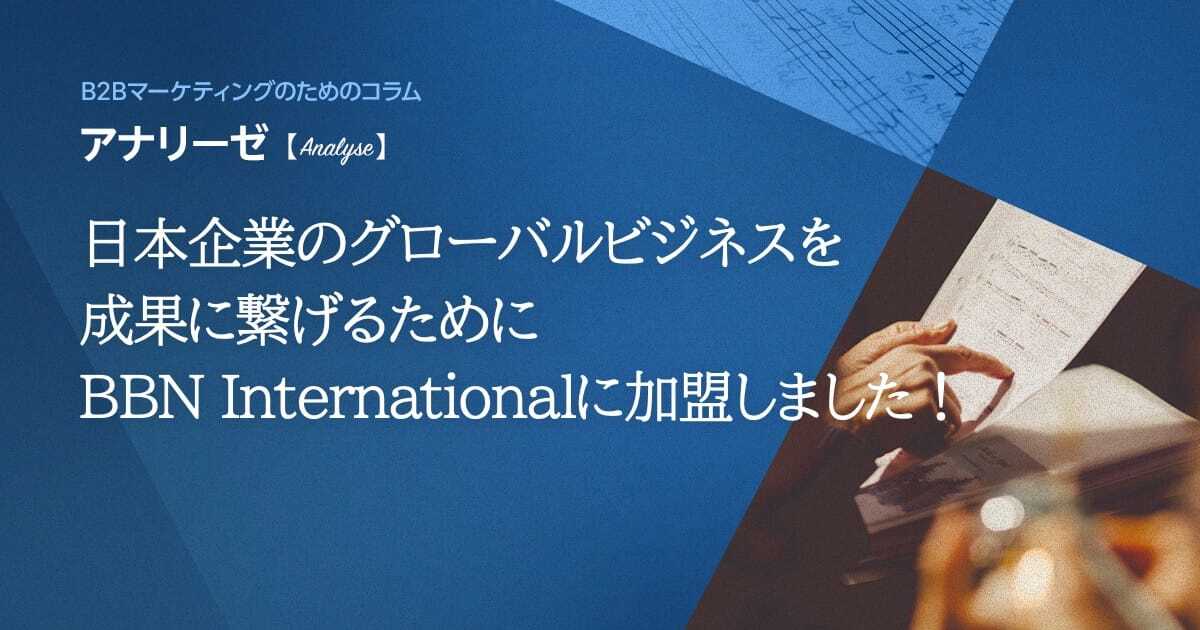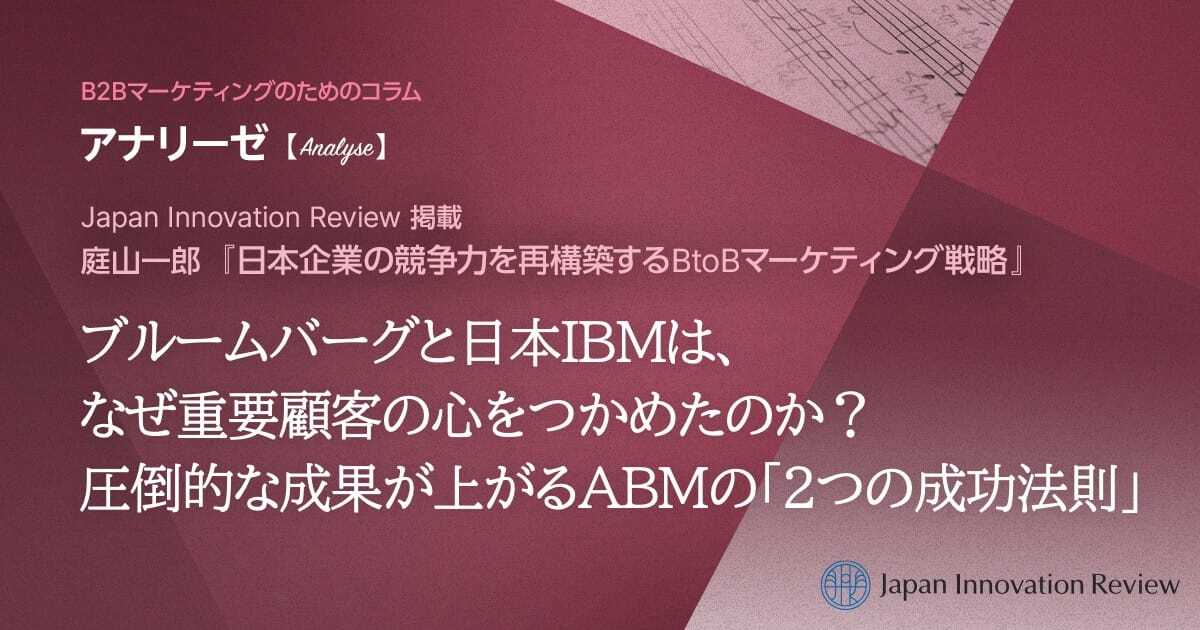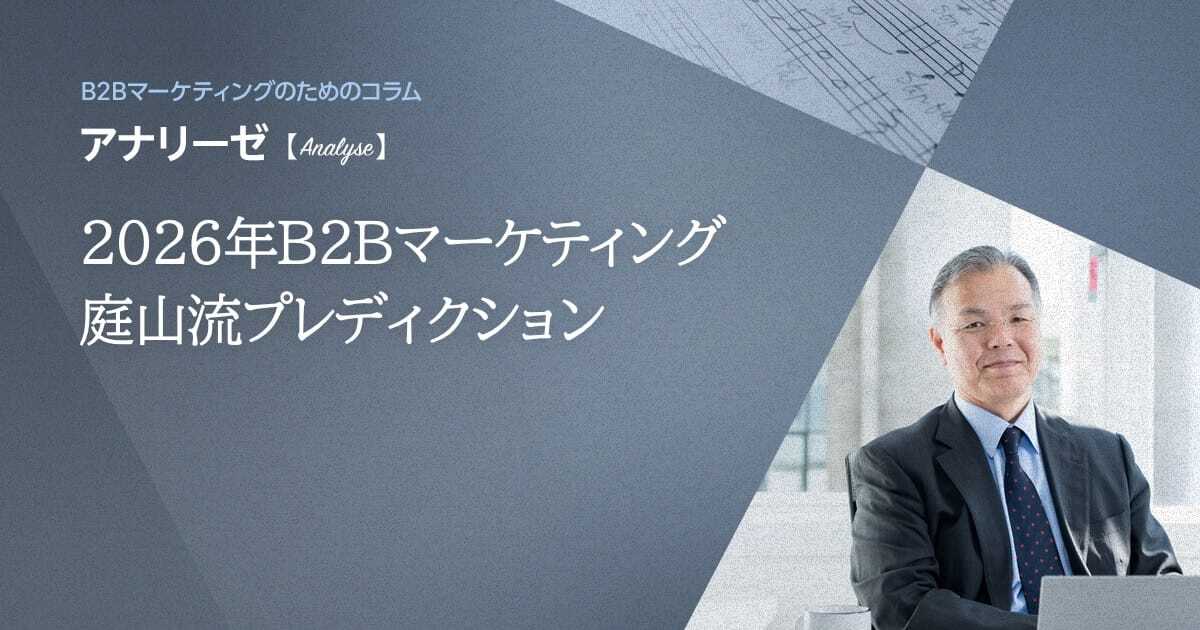世界のエンタープライズB2Bのメインストリーム
〝全社の顧客情報を統合し、マーケティングと営業の連携によって、定義されたターゲットアカウントからの売り上げ最大化を目指す戦略的マーケティング〟
これは、私が2016年に出版した『究極のBtoBマーケティング ABM』(日経BP)の中で紹介したABM(アカウントベースドマーケティング)の定義です。当時はまだABMの書籍は少なく、米国や英国で開催されるABMのカンファレンスの常連は、みんな顔見知りという状態でしたから、そのサークルの中でワイワイ言いながら定義を決めたことを覚えています。
ABMという言葉を初めて聞いたのは2012年の米ニューヨーク出張だったと思います。そして2013年に米サンフランシスコで開催されたマーケティングカンファレンスで、ABMを使ったキャンペーンのケーススタディーを見てびっくり仰天して、本格的に研究を始めました。それをまとめたのが冒頭の書籍です。これは世界で3冊目のABMに関する専門書です。
売り上げの70%は15%の顧客から
ABMはなぜB2Bマーケティングの本流といわれるほど、大きな存在になったのでしょうか? それはB2B企業の売り上げ構成比にあります。
SMB(Small and Medium Business)と呼ばれる中小企業は、比較的小口の顧客を多く持つ傾向がありますが、企業規模が大きくなると逆に売り上げに占める大口顧客のシェアが高くなります。その平均を取れば、売り上げの70%は上位15〜20%の顧客からもたらされています。これは、上位15%の顧客を競合に奪われてしまえば、企業は存続することが難しくなることを意味します。つまり、企業がその存続を懸けて大切にすべき顧客は、この15%ということになるのです。
B2Bの場合、パレートの法則がもっと極端に利いてきます。製造業であればトップ10%の顧客が売り上げの90%というケースも珍しくありません。となれば、その企業が絶対に守るべき顧客はその10%ということになります。売り上げの90%を失って存続できる企業などないからです。
その失ってはならない、大切な特定の企業にフォーカスしたマーケティング戦略がABMなのです。
出典:儲けの科学 The B2B Marketing 庭山一郎著(日経BP)より